


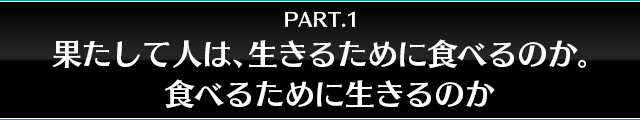
「哲学の話かしら、リンリー・クー先生」
「そんな難しい問題じゃないですよ。私は明日のご飯を心配しているんです」
わざとトゲのあるような言い方で返すと、エルマさんは喉の奥でククッと笑った。褐色の肌の上で、水色の目がスッと細くなる。私は、ライブラリーで観た古いファンタジー映画のワンシーンを思い出した。
あぁ、やっぱり素敵だなぁ――
神秘的な微笑みを目の前にして、心は、幸せな気持ちで一杯になった。
あえてフルネームで呼んで「先生」とまで付けたエルマさんが、私をからかっていたのはわかる。だからトゲのある言い方で抗議したつもりだったんだけれど――
ダメだ。そんなのはもうどうでも良くなってしまうくらい、エルマさんは素敵だ。
私は無宗教だけれど、聖なるものの前で人が嘘をつけなくなってしまう気持ちって、きっとこういう感じのことをいうんだろう。
そう考えると、整備ドックの片隅という油くさいこの場所でさえ、浄化された清々しい空間に思えてくるから不思議だ。
「食料の供給がそこまで危機的状況にあるなんて話は聞いてないわ」
「それは――しおしおのレタスとぼそぼそのおかゆなら半永久的な自給が可能です。でも食べることってそういうことじゃないじゃないですか。宇宙を航海する船内で食料を節約する気持ちは大事ですけど、食事の時間を楽しみにすることだって、同じくらい大事なことのはずです」
「今朝のメニューが本当に不満だったようね」
「いやぁやっぱりあの米ぬかパンだけはどうしても――ってそうじゃありません! 何を言わせるんですか! こと軍におけるメニューのマンネリ化は、士気に重大な影響を及ぼすと、私は言いたいんです!」
恒星間移民船『白鯨』が地球を飛び立ってそろそろ二年。
明確な目的地を持たない宇宙の旅は、移民船の中に形成された大都市一個分に相当する社会に禁欲的な生活を求めていたけれど、それでも市街区画に行けばある程度のメニューは揃っているし、食通などを気取らなければとくにストレスを感じるような状況にはない。食料自給のシステムは完成され、食材を合成する技術も二年の間にずいぶん進歩していたから、レタスとおかゆの話は極端だとしても、移民船の中の『食』事情が、今後何世代かの内に強迫的に統制されるようなこともないだろう。
でも――
きっとこれは、地球にいた頃も毎日フライドポテトだけを食べていれば満足できるような人が給食担当になったせいだと思うんだけれど、軍の中での食事については、レパートリーという面でとても貧困だった。
朝はシリアルとパンの繰り返し、昼も朝と同じようなメニューが続いて、そこに中国茶かたんぽぽコーヒーかの選択肢が付け加えられるだけ。夜なんかは出どころ不明な肉を揚げたものが、週に三回は出てくる始末だ。
軍隊行動時のレーションでさえ、昔はもっと娯楽的側面が重要視されていたはずなのに。
「エルマさんは、深夜にどうしてもアイスが食べたくなったらどうします?」
「そういう経験はないんだけれど」
「ないなら想像してください!」
「そうね――。軍の中で個人的な買い置きは禁止されているし、だからといって街に向かうなどというのは論外。それ以前に規定時間外の飲食は推奨されるものではないわ」
「ですよね。我慢するしかないですよね」
「ええ」
「ちょうどその時出撃がかかったらどうです?」
「どうって――なにが?」
「行動中も、きっとアイスのことが頭にチラついちゃいますよね?」
「いいえ。任務に集中するわ」
「すごく食べたかったんですよ。心残りになりませんか?」
「ならないとは思うけれど――。そうね、無理して想像力を働かせてみるなら、そのモチベーションを糧にして任務にあたるかしら。次の休暇になればアイスを食べることは可能なわけだし」
「あぅ――」
しまった、間違えた。根本から間違えてしまった。
食に対しての不満足がどれだけ軍での仕事に悪い影響を及ぼすかということを知って欲しかったのだけれど、きっと塩基配列のレベルからストイックが徹底されているエルマさんにとって、アイスのたとえ話はまったくリアリティがなかったようだ。
しかし私はあきらめない。
「でも次の休暇にさえ外出許可が出ないような、そんな絶望感が軍における今の『食』事情なんです!」
「なるほど。リンのいいたいことがわかってきたわ」
無表情でうなずくエルマさん。それが無関心だからではなくエルマさんなりの静かな納得であることはもう知っているので、私の口からは安堵の息が漏れる。
「エルマさんになら、わかってもらえると信じてました」
まぁ、ちょっとだけ手間取った感じはあったけれど――
「リンはマンネリの打破を目論んでいるのね」
「はい。週に一度――いえ、月に一度でいいですから、ぜひ、みなさんのためにお料理をするチャンスが欲しいんです! 私、必ず喜ばれるものを作ってみせますから!」
「――それを、私が給食担当者に許可させればいいわけ?」
「だって――私が言っても、きっと子供のわがままだって突っぱねられるだけなんですもん」
食堂に行けば「子供用のミルクはないぞ、あれは貴重品なんだ」と決まり文句のように言ってくる給仕係のおじさんたちの顔を思い出して、私はエルマさんから顔を背けた。むくれて歪んだ自分の表情を見られたくはなかったからだ。
「了解。他でもないリンの頼みなんだし、悪い結果にならないようやってみるわ」
軍においても、この移民船の中にあっても、それなりに高い地位にあるエルマさんは普段の会話でもあまり感情をあらわにすることはない。十三歳になったばかりの私のわずかな社会経験からでも、それが大人というものなんだろうと理解することはできる。けれど最近では、結局人柄なんじゃないかとも思うようになった。もとから多くを語らないのがエルマさんで――そして私がお願い事をしたこんな時だけは、最後に微笑んでくれるのもまたエルマさんなのだ。大人として感情を抑えているのではなく、逆に不器用で、ごまかすような感情表現ができない人なのだ。
「ありがとうございます、エルマさん!」
「メニューはどんなものを考えているの? 今の担当者の協力を得るのは難しいでしょうし、食材の調達さえ簡単じゃないわよ」
「もちろん、ちゃんと考えてますよ!」
私が胸を張ると、意外そうな顔をするエルマさんの様子が楽しかった。
「実はちょっとしたコネがあるんです。その気になれば夜中のアイスだって用意してくれる、強力なコネが――」
軍施設と市街区画はそれほど離れていない。大都市一つを丸々飲み込む巨大な移民船の内部は、それぞれのセクションが果たす機能別に整然と分けられていて、その間の移動もまた整備されている。
けれど市街区画に入ると話は別だった。
機能的という言葉とは真逆の風景がここにはある。
さすがに高層ビルとまではいかないけれど、それでも多くの人間の生活を収納することのできる建物が建ち並ぶ様子はまるで密林だった。それらの間を縫うようにして走る道路は無数にあって、マニアがあえて高いお金を払って手に入れた乗用車が行き交っている。雑然とした路地裏にはあくまで都市伝説だけれどノラ猫までいるっていう話だし、公園には植林がされ、時間によっては地球の空を真似たホログラフが投影されたりもする場所もある。
まるでここが宇宙を航行する船の中であることを忘れてしまうかのような空間――そしてもちろんそれを意図した意識的な不自由さを踏まえて建設されたこの『街』は、ノスタルジーであり、流浪の民となった人間たちへの配慮が形となった、設備、なのだ。
真似事かもしれないけれど、以前と同じ生活があれば、人は過去を振り返ることも少なくなるだろうし、虚空を彷徨う寂しさだって紛らわせることもできるということなんだろう。
街の大通りを抜けて、つい無意識にジャンク屋へと向かいかけた足を戻して、私は路地裏へと入った。そういえば掘り出し物が入ったとの連絡を受けていたことを思い出したのでかなり迷ったんだけれど、今日は軍のメカニックとしてではない、みんなのために一肌脱ぐ料理人としてここにやって来ているのだ。ささやかな使命感を心地よく感じながら、私は当初の目的どおりに歩みを進める。
物置をひっくり返したみたいにゴチャゴチャとした路地裏は、明るい活気にあふれていた。
通称、フィッシャーマンズアレイ。ここには、たくさんの露天が並んでいる。
いわゆる市場のようなもので、『白鯨』の上層部が推奨するスーパーなどでは決して見かけることのできない料理や食材が売られており、いつも結構な賑わいを見せていた。漁師(フィッシャーマンズ)といっても、もちろん鮮魚が卸されているわけではなく、乱雑に陳列された食物の数々は、各露店の店主が独自のルートで手に入れた合成物がほとんどだ。自家栽培された野菜や養殖された甲殻類もあるにはあるけれど、高価なそれらは売り物というより客寄せのための展示品でしかないことが多い。
中には化学者くずれで露天を営む人もいて、独自の技術で合成した食材を扱っているところもある。厳密にいえば違法。でもそれも社会生活の活気だととらえて暗黙のうちに了解する当局の姿勢には、移民船の居住者全員が無言の賞賛を送っている。
顔なじみの店主と挨拶をかわしながら人の間を縫って進むと、行く手に薄暗い一画が見えてくる。
路地裏の奥のさらに入り組んだ場所に、私が目指す店はあった。地球で暮らしていた頃は有名な大学の教授だった人が営む店で、やはり独自の技術で合成された様々な種類の肉を手に入れることができる。安全性も保証されていて、かつ味も良いので、私は特別な日の料理にはここの肉を使うことにしていた。
店の前にたどりつき、幾度となくかよってすっかり手に馴染んだ取っ手を握って扉を開ける。「やあやあ、また来たのかい」というおじさんの明るい声を期待して、私は笑顔で挨拶を返そうとした。
でも、声は聞こえてこない。それどころか店の中は暗くて、ガラスケースも空。合成とは思えない新鮮な輝きを放っている食材の数々は、見る影もなかった。
「――いらっしゃい」
留守だと思っていた店内に、まるで心霊現象のようなか細い声が聞こえた。思わずビクッと肩が跳ね上がったけれど、悲鳴をあげるまでにはいたらなかった。私は警戒心をマックスにして、店の奥に目を凝らす。
「あの――」
「すまないけど営業はしていないんだ。このとおり売れるものは何もないし、経営者も代わってね」
ガラスケースの谷間にはまり込むようにして、私の知らないおじさんが座っていた。私が見知った店主のジャンさんよりは少し若く見えるけれど、痩せた体を皺だらけの衣服で包み込んだその姿には、人生を重ねた老齢者の哀愁がにじみ出ているような気がした。
「ジャンさんはどうしたんですか?」
「さあ……私は知らない。何も知らない。私が知っていることなど、何もない」
会話しているはずなのに、おじさんは独り言のような喋り方をした。本当に失礼で申し訳ないけれど――ものすごく不気味だ。
「えっと――」
「トニー」
「え?」
「トニー・ニュース。私の名前だ」
「あ――。私はリンリー・クーです」
「リンリー――クー――」
「それでトニーさん。――もうここでお肉は買えないんですか?」
「うん。私にジャンのような合成技術はないからね。うん――ないんだ。私には何もないんだよ――」
「そうですか――。あ、いえ! 今のそうですかは、何もないと言ったトニーさんのことじゃなくて、お肉が買えないことをですね――」
「いいんだよ。ありがとう――」
恐らく私を気遣ってくれた優しい言葉。でも抑揚がなくて、その声はやっぱり不気味だった。
――困った、会話が続かない。
ジャンさんの居場所を聞きたいところだったけど、なんだか息苦しさが先に立って言葉が出てこない。
聞こえないように溜息をついて、私は「じゃあ」と立ち去ろうとした。
すると振り返った店の入り口に、いつの間にか数人の男の人たちが立っていた。派手なシャツ、ヨレヨレのスーツ、体にぴっちりとはり付いたタンクトップ――。これはあれだ。街のゴロツキと呼ばれる人たちのユニフォームというやつだ。
「さがしたぜトニー」
よれよれスーツさんが、目の前の私を完全に無視して奥のトニーさんに声をかけた。
「なんで――私をさがすんだ――。お前らの組織同士で話はついたはずだろう」
「ところがこの店の権利は、そんな簡単に収まるもんじゃなかったんだよ。気の毒にな」
よれよれさんの声は笑っていた。事態が飲み込めずトニーさんの方を振り返ると、その姿がガラスケースに手を付いて立ち上がるのが見えた。ひどく慌てたようすだった。
「逃げろ――リン!」
いきなり呼び捨てだ!
でもそんな批難の気持ちを打ち消す冷たい音が背中で聞こえた。時代遅れもはなはだしい金属音。ノスタルジーが徹底された街で使われる密造銃の銃口――――それを、私は背中越しに見た。
雄たけびのような声をあげて、トニーさんが突進してくる気配を感じた。
そちらに向かって私も反射的に走り出した。
次の瞬間、銃声が、店内にあふれかえった。
to be continued...