


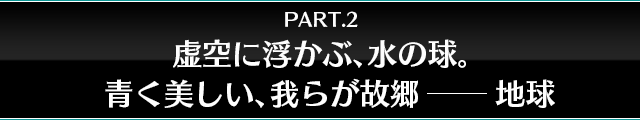
深淵に輝く一粒の宝石のように。暗闇に浮かぶ未来への道標のように。それは我々の心をとらえ、強く激しく揺さぶって離さない。
その姿を最後にこの目で見たのは、いつだったか。DM機関の慣熟試験で、静止軌道に上がった時か。それとも、月面基地の視察に訪れた時か。あるいは──
いずれにせよ、<白鯨>が抜錨した際のことではない。それだけは、たしかだ。あの時の我々は、ただ前だけを見ていた。行く手を塞ぐ、異星人たちの大兵力。その隙間に垣間見える、未知の深淵。それだけを目指して、旅立ったのだ。背後に浮かんでいる美しい故郷を、振り返る余裕はなかった。
そして、この先ももう我が目で見ることはない。あの戦いで、地球は消滅してしまったのだから──
ナギ・ケンタロウは、夢を見ていた。二年前に失った、故郷の夢だ。
夢とは、記憶という砂粒で構成される儚い風紋のようなものかもしれない。目覚めという風の前に崩れ去り、形を留めない。
暗闇のなかで目を覚ましたナギは、眼前から地球だけが失われたように感じ、喪失感に涙を流した。
(ああ、俺は──俺たちは、失ってしまった。地球を──)
そして、彼は思い出した。自分はいま睡眠から目覚めたのではない。激しい衝撃による気絶から、意識を取り戻したのだと。
彼の名はナギ・ケンタロウ。地球統合政府軍准将にして、地球種汎移民計画の一翼をになう巨大移民船<白鯨>の船長である。
地球種汎移民計画──それは、母星消滅という事態に備えて、地球に発生した生命種を他天体に移民させようという計画である。生存環境の消失がすべての種の絶滅に直結しないよう、万物の霊長たる人類が企図したものだ。
地球が消滅するという事態そのものは、統合政府にとって三十年以上前から予見されていたことだ。いや、むしろその予見こそが、統合政府の成立を後押ししたといってもよい。
かつて、地球人類は知ることになった──我々は宇宙の孤児ではなく、あまねく空間には、無数の隣人種族たちが息づいているのだと。
それは同時に、種の存亡の危機を知るということでもあった。無数の種族たちは、その身体を構成する物質の特徴から二つの勢力に分かれ、果てなき攻防を続けている。その攻防の焦点が、我々の地球に向けられる可能性が存在したのだ。
地球人類はこの時から、その種としてのリソースの大部分を、来たるべき未来のために集約した。地球統合政府を成立させ、人員と冨と資源とを、防衛と生存のための計画に振り分けたのだ。無論、統合政府の主流派となる勢力に、恭順しなかった者も多い。だが、この局面での小競り合いが未来の絶滅につながることを、全世界が理解していた。そのため、少数の不満や不公平の存在に、大多数が目と耳を塞ぐことになった。
こうして統合政府は、異星人勢力に抵抗する技術と、地球から脱出して生き延びる技術とを、両輪として発達させたのである。
なかでも人型機動兵器──ドールは、地球外の技術をもとに開発された異星人迎撃のための切り札だ。内燃機関を持たず、母艦からの出力転送で駆動するため、その躯体サイズの小型化に成功した汎用兵器である。そのため、十年足らずの間に相当数が生産され、地球圏防衛の体制が整った。
──はずであった。
(だが俺たちは──甘かったのかもしれん)
ナギの正直な述懐である。ドールとその母機となるDM機関の開発によって、人類の戦闘力は飛躍的に増強された。それも数倍から数十倍のスケールで、拡充されたのである。にも関わらず、人類はなにもできなかった。
地球近傍で行われた、二つの異星人勢力による激突。巨大な力と力のぶつかりあいの中で、人類の力はあまりにも矮小に過ぎた。龍と虎が相打つ足元で、アリ一匹が自分の巣を守り抜くことなど不可能だ。たとえ、それまでの数十倍の力を手に入れたアリであっても。
人類にできることは、数隻の移民船にすべてを託すことだけだった。逃げ延びてくれ、生き延びてくれ、どこかで繁栄してくれ、と。
その願いを背負っていたからこそ、ナギたち移民船クルーは後ろを振り向かず、地球から脱出したのである。背後で輝く閃光──母なる星が巨大な爆発に呑み込まれていく光景から目を背けて。
こうして、ナギが船長を勤める移民船<白鯨>は旅に出た。だが、二年の航海の末、白鯨はついに追撃を受けることになった。二つの異星人勢力のうちの一方が扱う、生体兵器群に襲撃されたのである。その生体兵器は恐るべきことに、居住区のアウターシェル──その分子間をすり抜けて、船内に侵入してきた。しかも、その一体一体が、中心部に反物質のコアを有している。うかつに撃破することすらできないその生体兵器群に潜入され、白鯨は深刻な危機を迎えた。
その事態から移民船を救ったのは、一人の青年だった。彼は勇敢な行動で生体兵器群を船内から排除し、乗機であるドールとともに行方不明になった。
だが、それで白鯨の危機が去ったわけではない。出航前に入手していた航宙図にも載っていない未知の惑星が、白鯨の眼前にあったのだ。
「それまで、なぜ誰も惑星の存在に気づかなかったのだ。奴らの追撃に意識を奪われていたためか? それとも──」
船体に深刻な損傷を追った白鯨には、その惑星の重力から逃れる術はなかった。ブリッジで指揮をとっていたナギは、不時着は不可避であると知り、あらゆる手段でダメージを最小限に抑えるよう操船した。
そして訪れた衝撃、そして暗転。気絶している間に、幸福な地球の夢を見て──そして、彼は目覚めたのである。
「こ、ここは──」
「おう、気がついたか、ナギ」
ナギにとって、聞き馴染んだ声が応える。白鯨の技師長であり、数十年来の友人でもあるヴァンダム中佐だ。上官と部下という関係になったものの、ともに階級を意識することのない関係が続いている。
「ヴァンダム、状況は──?」
「あまり良くないが──それでも幸運だったと言っていいだろうなぁ」
ヴァンダムは手短に自分たちが置かれた状況を語った。惑星の大気圏上層部で白鯨は四散して、ブロックごとに地表に落ちた。自分たちがいるのは、ブリッジとその周辺のわずかな区画のみ。目視では、周囲に他のブロックは見当たらない。
「それで──惑星の環境は? 生存には適しているのか?」
ヴァンダムは無言で右手を指さした。そちらを見て、ナギは絶句する。外壁に大きな亀裂が走っており、その隙間から夜空が見えているのだ。
「空気は──呼吸可能なのか」
「それだけじゃない。気温も摂氏二十度、重力は0.94G、放射線レベルも既定値以下──なんの防備もなく、生きていけるようだ」
「そんな──未知の惑星でそんな偶然が──」
「偶然でなきゃ、誰かの意図か──ご親切に感謝しなけりゃならんな」
ヴァンダムが言うとおりだった。船が四散したのは、痛恨の極みだ。地球種を移民させるための旅が、これ以上続けられないことを意味している。だが、その終着点が環境に手を加えることなく生存可能な惑星だったというのは、奇跡というだけではすまされない。神か悪魔か、何者かの見えざる手が働いているとしか、ナギには思えなかった。
「他のブリッジクルーは?」
「みんな働いてるよ。周辺の偵察、動力の復帰、使える物資の回収──やるこたぁ、いくらでもあるからな。あと気絶してるのは──」
ナギからほど近い席で、コンソールにつっぷしている若い女性オペレーターがいる。たしか、メイ少尉とかいう新人だったはずだ。
「俺が最後から二番目か──歳はとりたくないものだな」
「なに言ってやがる!」
ヴァンダムが、ナギの背を乱暴に叩いた。荒っぽい賞賛も当然である。大気圏突入に揺れるブリッジで、衝撃に耐えながら最後まで操船していたのが、ナギだったのだ。他のクルーが対衝撃姿勢をとっていたのに、彼にはその余裕すらなかった。その分、覚醒が遅れるのも無理からぬところだ。
もっとも、やはり衝撃に備えることをせずに補機のみとなったDM機関の制御を続けていた技師長は、ブリッジクルーの中で最初に目覚めたらしい。頑強な体は、他の者とは規格が異なるのだろう。
「う、ううん──」
か細い声が、最後の一人の覚醒を告げた。メイが起き上がって周りを見渡している。どうやら、ブリッジクルーは全員無事だったようだ。
「船長、技師長──!」
メイがあわてて直立不動になり、敬礼する。ナギは苦笑いした。
「こんなところで、礼儀だの気にする必要はない」
「まったくだぜ。俺たちゃ全員そろって、ロビンソン・クルーソーになっちまったようなもんだからな」
「は、はい、わかりました!」
メイはふたたび敬礼しようとして、挙げかけた手を止め、頭を下げた。どうやら素直な性格の若者らしい。ナギは微笑みかけて、宇宙空間に消えていった若者のことを思い出した。幼い頃から知っていた、彼のおかげで白鯨は救われたのだ。
(いや、救われた──と思うのはまだ早いな。我々はこれから、自らを救っていかねばならないのだ。すまんが、いまはあいつのことは忘れよう──)
ナギはてきぱきと、思いついた事々についての指示を出し始めた。周辺に散っていたブリッジクルーたちも、次々と集まってきて、ナギの指令を求めはじめる。そう、彼らは自分自身を救っていかなければならないのだ。ロビンソン・クルーソーとは異なり、海の向こうに帰るべき祖国があるわけではないのだから──。
白鯨という船の設計者に感謝するべきだとしたら、まず船体各所に人工重力発生装置を備えていた先見の明に対してだろう。
もともと、移民船の旅は長期に渡ることが予期されていた。そのため、クルーが無重力環境に適応してしまうことを回避するための措置だった。
人工重力発生装置は、多大なエネルギーを消費する。そのため、不要論も根強かったのだが、彼らの移民が地球種の拡散と維持が目的である以上、生活様式を存続させることも重要だったのだ。だからこそ、居住ブロック内部は地球上の都市を再現したものとなっており、いずれは移民先の惑星上に定位させることまで想定した構造となっていた。
そうした構造は、船のリソースに負担を強いるものではあったが、DM機関という新技術はそれに耐え抜いた。
ともあれ、その人工重力発生装置が、ほぼ1Gの惑星表面への落着の衝撃を吸収した。ブリッジにも独立したその機能があったため、大破をまぬがれたのだ。四散した他のブロックも、無事なものは少なくないはずだ。
「我々はまず、他のブロックを見つけなくてはならない。第一に居住ブロック、第二にDM機関部、第三に──ライフだ」
固唾を呑んで指示を待つブリッジクルーたちに、ナギは説明した。居住ブロックは、この惑星上で生きていくための拠点となる。DM機関部は主機が大破したものの、まだ補機が存在する。文明的な生活を営みたければ、拠点とエネルギーは欠かせない。そして──
「ライフか、あれの発見は急がねえとな」
ヴァンダムが腕組みして深刻そうにつぶやく。ライフとはある意味、移民船の最重要貨物だ。地球から旅立った移民の大部分は、このライフの内部で眠っているのだから。
「私、兄と両親が眠っているんです。だから──」
メイが不安そうにつぶやく。白鯨の船内で目覚めていたのは、操船クルーと戦闘要員、それにライフのシステム保守要員だけだ。当然、家族がそこで眠っているケースも珍しくない。
しかし、落着の衝撃に耐えたとしても、エネルギーが枯渇すれば、システムが停止してしまう。眠っている人々を救うためには、なんとしてもそれまでにライフを発見しなければならない。残された猶予は短くないが、決して長くもないのだ。
「よし、それじゃあ他ブロックの捜索を開始する。まず──」
そう指示を出しかけて、ナギは息を呑んだ。
「おい、ナギ──」
「ああ、わかっている」
ヴァンダムも周囲の気配に気づいたようだ。地球の夜と同じく、わずかな星明かりにのみ照らされた異郷の夜。そのなかに、何者かが息づいている。荒い息と地面を踏みしめる音。気配を殺している様子はないところからすると、知的生命体ではあるまい。追っ手の異星人ではないとすると、原生生物だろうか。
だが、地球人を殲滅しようと迫ってくる異星人であろうと、捕食しようと近付いてくる原生生物であろうと、その危険性に違いはない。ここが未知の世界である以上、迫り来る脅威からは自分の力で身を守らねばならないのだ。
「──各自、携行武器は装備してあるな?」
ナギの言葉に一同がうなずく。
「よし、ではこの場で迎撃する。遮蔽物のない外では、不利だからな」
おそらく迫り来る相手は、夜行性の生物だろう。乱戦になったら、勝ち目はない。ナギはパニックが起こらないよう、努めて冷静な声で告げた。
「総員、背を向け合って円陣を組むぞ。正面から来るヤツだけを迎撃しろ、横と背中は周
りにまかせるんだ──来るぞ!」
ブリッジ外壁に空いたいくつかの亀裂から、人間に近いサイズの影が飛び込んできた。後に“シルネア”と名付けられる原生生物だ。日中は木にぶら下がるなどして、大人しい生物だが、夜には凶暴になる。機動兵器があれば恐るるに足りない存在だが、ブリッジに備え付けられているのは、バトルアサルトやアタックアサルトといった、小口径の携行火器のみである。宇宙船のブリッジで想定される戦闘など、叛乱鎮圧や白兵戦のみだったのだから、無理もない。大出力の武器を使用して、気密を破ってしまう方が深刻な問題と考えられていたのだ。
だが、気密のことなどまったく考える必要のない状況下での戦闘が勃発した。それでも、ブリッジクルーたちは勇敢に応戦した。ナギの指示が的確で、落ち着いて迎撃できたことが大きかったのだろう。巨大な亀裂の方を向き、強力なストライクアサルトを手に仁王立ちするヴァンダムの姿も、若いクルーたちには頼もしかったに違いない。技師長でありながら、歴戦の兵士としての風格を持つ彼がトリガーを引く度、夜闇のなかで未知の生物が吹き飛ばされていった。
(どうやら、持ちこたえられそうだな──)
ナギがそう考えたのを、油断と評するのは酷であっただろう。この未知の惑星に関する知識が、彼らにとってはあまりにも不足しすぎているのだから。
いかなる遺伝子の悪戯か、この惑星では様々な種族に突然変異が発生する。身体能力や知性、時には体のサイズまでが同種の生物群を超越した個体が棲息しているのだ。この時、白鯨船橋の隔壁のすぐ外に現れたのも、そうした超越者(オーバード)だった。
巨大な──あまりにも巨大すぎるその原生生物が、隔壁の亀裂の向こうに現れた時、ナギたちは恐怖を感じなかった。現実感が乏しいと、脳は処理能力が低下するらしい。危険を感じるべき神経が麻痺したのか、一同はその巨大生物に見とれてしまった。
あるいは、それが神々の眷族に思えていたのかもしれない。巨大生物が、前脚とおぼしき部位を振り上げ──そして振り下ろしてくるまで、ナギたちは一歩も動けずにいた。
to be continued...