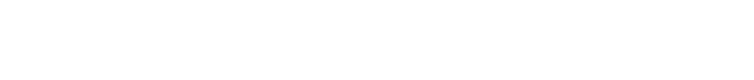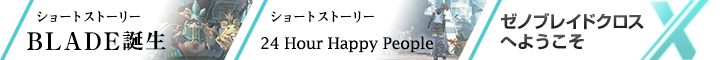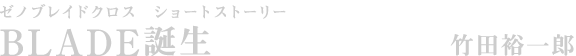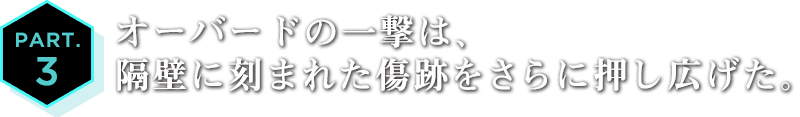複合金属が捻れ、破砕される耳障りな音が、ナギやブリッジクルーたちの意識を現実の地平へと引き戻す。彼らの眼前で、押し広げられた亀裂からオーバードが押し入ってこようとしていた。
「頭だ、頭を狙え! 一点集中で仕留めるぞ!」
ヴァンダムが吠えた。同時に、ストライクアサルトを巨大生物の頭部に向けて連射する。その火線が、狙うべき場所の目印となった。ヴァンダムの言葉を口に出して支持するようなことはせず、ナギもまた同じ場所を狙点にさだめて、銃爪を引く。周囲の者たちもそれに続いた。
十数人が放つ火線が集中し、オーバードは怯んだように見えた。だが、それも一瞬。煩わしそうに頭を振ると、巨大なモンスターは力尽くで上半身をブリッジ内部にねじ込んできた。
「退避しろ! ブリッジを放棄する!」
「ちっ、それしかねえか!」
ナギの言葉に、ヴァンダムが同意する。ブリッジはオーバードの蹂躙によって、いまにも崩壊しそうだ。しかし、巨体が亀裂を押し広げている今なら、動きが鈍い。ヴァンダムが先頭、ナギが殿(しんがり)でブリッジクルーたちは逃げ出した。オーバードと反対方向へ。
ブリッジの外に脚を踏み出して、ようやくナギは見た──二年の放浪の果てに、自分たちが到達した未知の大地を。
傷つき、四散した白鯨がふたたび離床することは、もはや不可能だ。だとしたら、自分たちはこの大地で生きていかねばならない。もしかしたら、それは新たな宇宙船を建造するまでの間だけかもしれない。それでも、決して短い間になることはないはずだ。
暗夜に広がる荒涼とした大地。踏みしめる岩盤のかたさも、どこか地球のそれとは異なるように感じる。記憶にないシルエットの植物が生い茂る彼方には、木々の枝のように空中に突き出した崖がある。およそ物理法則を無視した光景のようにも見えるが、この星にはこの星の法則があるのだろう。
見上げてみれば、分厚い雲の向こうに巨大な衛星が浮かんでいる。視直径で測れば、地球の月の数十倍はあるように思えた。
(──いや、目の前にあるものひとつひとつを、地球のものと比べるのはやめにしよう。そんなことには、なんの意味もない)
かつての物差しで新世界を測ることの無意味さを、ナギは噛みしめた。いま重要なのは、眼前に存在するものが、生存という自分たちの目的に有益か、不利益か、それを見定めることだけだ。
そして、明らかに不利益な脅威が、すぐ背後に迫っている。
「ええい、お前ら鍛え方が足りん! この場を生き抜いたら、腕立て一億回だ!」
巨大なオーバードから逃げようとして転倒した者たちを、ヴァンダムが強引に立たせている。オーバードと腕立て一億回、どちらにより深刻な恐怖を感じたのか、立ち上がった者たちは必死で前へと進んでいく。
背後ではブリッジがオーバードに踏みにじられ、ひしゃげていく轟音が響いている。ナギたちにとって、それは単なる破壊ですまされるものではない。地球を脱出してからの二年間、職場であり、生活の場であった場所が失われていく音だ。
(持ち出したいデータや機材も山ほどあったというのに──)
そして、持ち出すことのかなわない愛着や思い出も詰まっている。それらのすべてが、一体のオーバードに踏みにじられた。
ナギは悔しさのあまり、奥歯をかみしめる。だが、それらのものより大切なのは、クルーひとりひとりの生命だ。いまはまず、自分たちが生き延びることこそを考えなければならない。
「技師長、みなを頼んだぞ!」
「お、おい、ナギ!」
前方はヴァンダムにまかせ、最後尾にいたナギは踏みとどまり、オーバードの方を振り向いた。そして、アタックアサルトをかまえる。
「先住者くん! 新参者がこのような振る舞いに出て、失礼かもしれんが──我らもこの地で生き抜いていかねばならん! その資格があるかどうか、実力で証明してみせよう」
言葉が通じたとは思えない。事実、オーバードはナギの存在に、なんらかの反応を示したかのようには見えなかった。ただ、行く手にいる獲物として、目を留めただけだ。だが、たしかに脚を止めて、彼の方を見下ろした。
──それだけで充分だった。
慎重に狙点をさだめたナギは、正面に相対したオーバードの目を撃ち抜いた。直撃する寸前に目蓋を閉じたようだが、高速徹甲弾が貫通した。
「────!」
人間の文字では再現しがたい咆吼が、オーバードの口蓋から放たれる。それは悲鳴か、あるいは怒りの声か。どちらにしても、彼の敵意はナギのみに向けられた。
「そうだ、それでいい。俺だけを狙え! この命ひとつで若い連中を救えるのなら、安いもんだ!」
ナギは第二射を放とうと、ふたたびアタックアサルトをかまえた。だが、それで残りの目を撃ち抜こうというのは考えが甘すぎたようだ。オーバードはそれ以上、近付こうとはせず、手近な金属片を投げつけてきた。
オーバードのサイズと比較したら小さな金属片に見えたが、それは白鯨の隔壁の一枚だった。ナギの身長をはるかに上回る隔壁が大地に突き刺さり、撃ち砕かれた岩の破片が彼の全身を打った。
「ぐううう──」
たまらずに吹っ飛ばされたナギに、オーバードがゆっくりと近付いてくる。警戒しているようだが、すでにナギの手にアタックアサルトはない。岩塊に直撃され、へし折れてしまった。もはや反撃の手段は残されていない。
「まあいい。思ったよりはずいぶん時間を稼げた。後を頼んだぞ、技師長──」
観念しつつも、目を閉じようとはしない。自分にとどめを刺そうと近付いてくるオーバードから、最後の瞬間まで目をそらさぬ決意で対峙する。
ナギにとって、そのオーバードは敵ではない。ただ、未知の大地で巡り会い、互いの生存をかけてぶつかりあっただけだ。憎しみも恨みもなく、訪れる瞬間をただ待った。
だが、互いの運命は一瞬のうちに変転した。
オーバードの右手から、大出力の砲撃が撃ち込まれてきたのだ。重機関砲の掃射を半身に浴びた巨大生物は、その場に倒れ込んだ。硝煙と、記憶にない生々しい匂いとが、ナギの鼻孔を刺激する。
(これが、この星の生物の血の匂いなのか──ヘモグロビンとは異なるなにかで構成されているようだ)
一瞬前まで、生命の危機にさらされていたとは思えないほど、ナギは冷静に考えた。そんな彼の思考を、現実に引き戻したのは鋼鉄の足音だ。
ナギの命を救った機体──地球製のドールが二機、夜闇のなかでもわかるあざやかな姿を現した。どちらも“AD0130 Formula.ST”と呼ばれる汎用機だ。
「船長──ナギ准将ですね!」
手前にいるAD0130の外部出力スピーカーから、パイロットの声が響いてくる。ナギには、その声に覚えがあった。
「イリーナ──イリーナ・アクロフ中尉か!」
その後、ナギの無事を知ったヴァンダムとブリッジクルーたちが戻ってきた。ドールから降りてきたイリーナ中尉と、その部下であるグイン少尉はクルー全員にとって、旧知の仲だ。一同は手荒く互いの背中や肩をたたき合い、再会を喜んだ。
「──それにしても、いいところへ来てくれたな」
「俺の機体のガンカメラに、ブリッジが落ちていく様子が映ってたんです。画像解析で落着軌道を解析して、急いでやってきました」
ナギの言葉に、グインが答える。
「グインにしちゃ、大手柄だよ。あ、偉いのはあんたじゃなくて、機体の方か」
「ええ〜〜、ひどいっすよ、中尉!」
イリーナとグインは上官と部下というだけでなく、入営する以前からの知人同士だったらしい。二人の会話には、仲の良い姉と弟のような空気がにじんでいた。
「それでお前ら、居住区の方はどうなっとるんだ?」
ヴァンダムの言葉に、イリーナとグインは表情を引き締めた。白鯨の船体が崩壊する前、二人が所属するドール小隊は、居住区に侵入した異星人の生体兵器群を迎撃していたのだ。
「健在です。ですが──」
イリーナは説明をはじめた。ブリッジ区画と同じく、居住区にも人工重力発生装置があるため、地表への軟着陸は無事成功した。むしろ、移民計画当初から居住可能な惑星に降下させることを想定した仕様になっているため、成功する可能性は高かったのだ。だが、深刻な問題が発生した。居住区全域にエネルギーを供給するDM機関が大破してしまったのである。
「では、市街地はどうなっている──?」
「予備動力で、最低限のライフラインは維持しています。ですが、アウターシェルの展開は不可能。予備動力もいつまで保つかわかりません」
「その上、原生生物が次々と襲いかかってきて、ドール隊はその相手で手一杯なんですよ!」
ナギは黙り込んだ。居住区が落着に成功したのは朗報だが、状況はとても楽観視できるものではない。代わって、ヴァンダムが怒鳴りつける。
「そんな状況で、お前らはなにをやっとるんだ。なんで俺たちの救援なんかに来た!」
「技師長にそうドヤされるのは覚悟の上です。ですが、我々に必要なのは、一機二機のドールよりもまず指導者なんです。誰かが指揮をとってくれなくては、いずれは全滅します」
「そう思って俺たち、原生動物の群れのなかを突っ切ってきたんです。ブリッジにたどりつけば、きっと船長が──ナギ准将がいるって──」
イリーナやグインが、すがりつくような目をナギに向ける。この二人とて歳は若いが、二年前の異星人との攻防や、その後の追撃戦を生き残ってきた優秀な戦士だ。その彼らをして、不安を隠せなくなるほどの事態なのだ。
(せめて、エルマがいてくれたらな──)
生体兵器群を迎撃するなか、白鯨を救うために行方不明になった英雄。彼と行動をともにしていた部下のことを、ナギは思った。大佐の階級を得ているエルマは、ナギの片腕のような存在だ。イリーナやグインからの信頼もあつく、彼女が居住区の方にいてくれれば、どれほど心強かったことか。
だが、現実問題、エルマは行方不明だ。二年前の地球における戦闘で、そして今回の落着で、彼らは多くの人材を失った。いまここにいる人間だけで、すべてを乗り切らねばならない。
「よし、わかった。俺は二人と一緒に居住区へ向かう。技師長はクルーをまとめて、後から来てくれ」
「──たしかに、全員がドール二機に分乗するわけにはいかねえしなぁ。わかった」
ナギの言葉に、ヴァンダムがうなずいた。
──こうして、ナギはグインのAD0130の肩に乗って、イリーナ機とともに居住区を目指した。もともと、ドールのほとんどは単座の機体であり、二人以上の人間を乗せるようにはできていない。コクピットに乗れない以上、肩部装甲にしがみつくしかないのだ。
イリーナ機が周辺警戒しながら先導し、グイン機は慎重にそれに続いた。
「グイン少尉、もっと速度をあげてもいいんだぞ」
「えっ、でも──」
「グイン! 船長がそう言ってるんだ。先を急ぐぞ!」
「わ、わかりました!」
イリーナ機とグイン機は、そろってスピードをあげた。大気圏内用の飛行可能なドールがあれば、もっと高速で安定した移動ができただろう。だが、生体兵器群を迎撃した最後の戦いで、彼らのAD0130に施されていたのは宙間戦闘装備だった。大地を行くには、二本の脚で進むしかない。当然、機体にしがみついている者が受ける震動は、すさまじいものとなる。ショックアブソーバーが完備されたコクピットですら、不慣れな新兵だとごく短時間しか耐えられないものなのだ。
だが、ナギはその過酷な状況に耐えた。こうしているうちにも、居住区はどのような被害を受けていることか。耐えねばならぬ状況であるならば、ただ耐える以外の選択肢は存在しない。それを理解しているからこそ、イリーナも先を急がせたのだ。
激しい震動と衝撃のなか、ナギは左肩に痛みを覚えた。いや、それは錯覚でしかない。たしかにそこには古い戦傷があったのだが、もう痛まないようになっている。
(あいつがいてくれたらな──)
ナギは旧友の顔を思い出した。移民計画に重要な要素を開発した技術者。彼の存在なくして、計画の実現はなしえなかっただろう。だが、その人物本人は、移民船に乗ることはなかった。病に倒れ、計画発動前に命数を使いはたしたのだ。
(だが、あいつは幸せだったのかもしれん。地球が消滅するところを見ずにすんだのだから──)
そう思いかけて、ナギは頭を振った。そんなはずはない。旧友は地球の滅亡を、あり得る可能性として理解していた。その上で、それを乗り越えた先に地球種を存続させる研究を続けたのだ──残り少ない命のすべてを賭けて。
ナギたちがなすべきは、災厄を見ずにすんだ者をうらやむことではない。災厄を越えた先に、すべてをつなぐことだ。生命を、歴史を、文化を、地球という惑星に発生した生命種が存在したという証しを、未来へ──。
「その使命の重さを思えば、揺れに耐えることくらい──」
そうつぶやきかけて、ナギは顔をしかめた。舌をかんでしまったのだ。
「ナギ船長、前方、見えますか?」
グインの声に、ナギは前を見た。まだ夜明け前、闇の中にいくつも灯りがともっている。いや、あれは炎だ。白鯨の居住区が燃えている。
「あれは──戦闘か?」
「ええ、原生生物が入り込んで、暴れてるんです。船長を降ろして、俺も迎撃に加わります!」
「馬鹿者! 戦闘要員を無駄にしてどうする。俺を連れて行け、武器庫でもドール格納庫でもかまわん! 戦う術のあるところへ!」
だが、ナギの決意も虚しかった。居住区にもドールを整備する区画は用意されていたが、機体はすべて出払っていた。残されている武器も小口径の火器ばかりだった。
ナギは自ら戦うことをあきらめ、戦闘の指揮をとることに専念した。
「──住宅エリアに取り残された者はいないのだな! よし、あそこの防衛は放棄してかまわん! 工業エリアのライフラインを重点的に防衛するんだ! ラオのドール隊もそっちへまわせ!」
ナギが現れたことによる、状況の変化はめざましかった。もともと、ここにいたのは白鯨の操船クルーがその大半である。それぞれに特殊技能を持ち、意識も高い。原生生物の襲撃を受けた当初、彼らを苦しめたのは混乱と、指揮系統の不在であったのだ。
ナギはまず、居住区のすべてを守り切ることをあきらめた。非戦闘員を工業エリアの頑強な建造物のなかに集めて、その周囲に防衛線を構築した。そして、イリーナ隊やラオ隊、ダグ隊といった限られたドール部隊を的確に配置して、守り抜いたのである。
──そして、夜が明けた。
おそらく夜行性であったのだろう原生生物が、恒星の光を浴びて居住区の外へ去って行く。また夜がくれば襲ってくるかもしれないが、それまではねぐらに引っ込んでいるだろう。朝の光は、人類の味方だ。昼のうちに防備を整え、状況を調査し、次の夜にはもっと効率的な防衛ができるようになるだろう。
ナギは近くにいた事務官たちに指令して、まず名簿を作らせた。白鯨のクルーのうち、どれだけが生きて、ここに集まったのか、まず確認しなければならない。そして、彼らに役割をふって、組織を整え、そして──
そして、いましなければならないことを思いついた。
「なあ、この居住区、たしかモデルがあったはずだな──」
ナギの言葉に、事務官はうなずいた。白鯨の居住区を建設するにあたっては、ある街を参考としていた。街路の構造が、まったくそのままというわけではない。だが、印象的なランドマークや、市街の雰囲気といったものは、たしかに受け継がれている。
「よし、ここはもう居住区じゃない、俺たちの街だ。そして、街には名前がいる」
事務官や戦闘員たち、操船クルー、そうした人々がナギを見つめていた。イリーナやグインの姿もある。ナギは彼らに向かって、宣言した。
「ここはニューロサンゼルス。これから、NLAの復興を開始する──!」
![]()