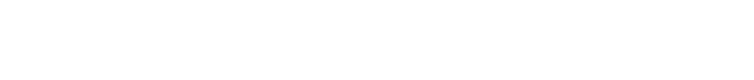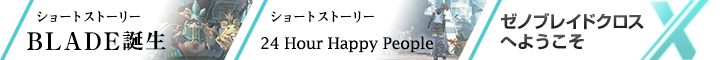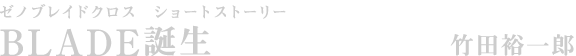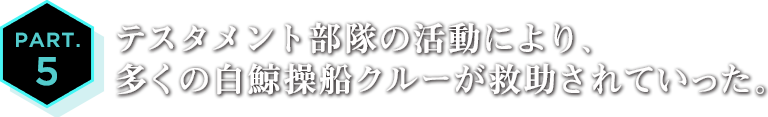彼らが新たな住人となり、生活の拠点としてのNLAが整備されていく。そんな中で第四、第五の部隊が編成された。オーバードと呼ばれる強大な原生生物を駆逐するアヴァランチ部隊と、兵器や武装を開発するアームズ部隊だ。ナギとともに活動していたダグは、幾度かのオーバードとの交戦経験を買われて、アヴァランチに転属することになった。
こうして、地球人がこの惑星で暮らしていく環境は整えられていったが、さらに深刻化した問題もある。エネルギー供給だ。人口が増え、活動が多様化していくに連れ、それが無視できない問題となっていくのは自明の理だ。
「──そろそろ限界だ。なんとかしてくれ、船長」
「限界なのは、補佐官に言われなくてもわかっている」
モーリス・ショーソンとナギ・ケンタロウは、何度目になるのかわからない会話を繰り返した。船がないのに船長、大統領もいないのに大統領補佐官──そう呼び合うのも奇妙な話だ。だが、新たな公的立場を決めるのも面倒で、そう呼び合う状態が続いている。モーリスもナギも、互いに相手を嫌い──というほどではないが、波長があわないと感じ、煙たく思い合っていた。それでも、NLAの民政や軍事を指導できる人材は他になく、嫌々ながらも密に顔をつきあわせて、やっていかねばならない関係だった。
(ヴァンダムのやつめ、うまく逃げおって──)
自分に代わる軍事的責任者の座を押しつけようと思っていたヴァンダムは、アームズ部隊の創設以来、嬉々としてそちらの活動にとりくんでいる。もともと技師長だったことを思えば無理もないのだが、結果としてデスクワークの多忙を強いられたナギにとっては、面白くない。
とはいえ好き嫌いを言っていられる状況でもなく、ナギはモーリスと会議を続け、ついに避けられない課題に直面させられた。
「──率直に言って、あとどのくらい保つ?」
「一週間といったところだ。それを超えれば、市民生活が破綻する」
もちろん、エネルギー不足を解決するには、供給を制限するという方策もある。だが、モーリスもナギも、それは避けたいと考えていた。地球を失うという悲劇から、まだたった二年しか経っていないのだ。そんな状況下で。白鯨のクルーは見知らぬ惑星での新天地建設という難事業にとりくんでいる。せめて、NLAで暮らす日常生活くらいは、故郷にいた時と同様の快適さを与えたい。耐乏生活というものは急速に人心を荒廃させていく。二人とも、何よりもそれを怖れていたのだ。
「わかった。例の計画を五日で完遂する」
「ああ、その言葉を待っていた。頼んだぞ、船長」
例の計画──それは、白鯨のエンジンを回収するというものだった。リンリー・クーという少女が語った目撃情報をもとに調査したところ、NLAと同じ大陸にエンジンブロックが落着していることが判明したのだ。異星人の追撃部隊によって、白鯨の主機は大破してしまっていたが、補機だけでもNLAのエネルギー事情を支えるには十分だ。
白鯨の主機や補機に使われているDM機関──高効率、高出力を誇るこの動力炉が入手できれば、NLAのエネルギー問題は一気に解決される。だが、その回収計画が即座に実行されるには、二つの問題があった。
第一に、輸送問題。DM機関は、核融合炉などに比べると極めて小型軽量のものだ。それでも巨大な移民船のエンジンであり、1Gに近い重力下での回収・運搬には技術的問題が多い。
第二に、計画を阻むものの存在である。補機は海上の浅瀬地帯に落着した。それ故に、奇跡的といってもよいくらい損傷が少なかったのだが、そこは海棲生物の群生地だったのだ。安全な回収作業を行うためには、これらを排除する必要があった。
そのため、ナギはアームズ部隊を編成して、回収作業に投入する機材やドールの整備を急がせたのだ。深刻化するエネルギー問題が限界を迎える瞬間と、どちらが早いか、時間との戦いだった。
こうして決断から五日の後、ナギ自らが率いるテスタメント部隊は、NLAから進発した。イリーナにダグ、ラオ、グイン──戦力の中核となるドール乗りには、精鋭を選んだ。もちろん、ナギ自身もドールに搭乗している。ライトフレームの機体のなかではもっとも性能が高いFormula.ZEROだ。もっとも、ナギはそれでも満足していない。
(これからも、この惑星で生きていくには、もっと高性能なドールが──それも相当数が必要だな。白鯨の研究開発ブロックが見つかれば、試験中だった高性能機が手に入るものを──)
だが、もはや作戦決行を先延ばしにできない以上、現有戦力でやるしかない。幸い、メンバーについては最精鋭の人選ができた。
「──こちらT001、間もなく作戦地域に到着する」
ドールの歩行による三日の踏破を経て、部隊は目的地の至近に到達した。崖のような地形で待機して、ホッパーカメラを打ち上げる。転送されてきた映像が、ドールのコクピット内に投映される。
「よし、まだ健在だな」
事前偵察で確認した通り、崖下の浅瀬には白鯨の補機が横倒しになっていた。遠隔によるステータス確認では、故障箇所もなく正常稼働しているようだ。
「作戦開始まで0300、各自カウントゼロと同時に作戦を開始せよ」
ナギが最終確認の通信を送り、部下たちが口々に了解の返信を送ってくる。人類同士や、高度な文明を持つ異星人相手の作戦と違って、原生生物に傍受されることはない。
(通信封鎖しなくてもすむというのは、気が楽になるものだな──)
部下たちもそのことは知っている。残りわずかな時間の間にも、軽口が飛び交った。
「この作戦が成功すれば、もう節約の必要もなくなるんですね!」
「グイン、あんた節約なんかしてたの? 毎日、好き放題食べまくってると思ってたのに」
「イリーナ中尉、ひどいっすよ! そんな不摂生してる男が、こんなスリムなボディ維持できてるわけないでしょう!」
「スリムねぇ──グイン、お前さんはもっと筋肉つけた方がいい。そんな細腕じゃイリーナになにかあっても、護ってやれないぞ」
ダグのツッコミに、グインが咳き込む声が聞こえた。彼らのやりとりに、ラオは加わろうとはしない。
(昔はもっと、快活な男だったような気がするんだがな──)
ナギがそんなことを考えながら、モニターをながめていると、ついにカウンター表示が一桁になった。ゼロになるとともに叫ぶ。
「よし、作戦開始だ!」
崖の上から、五機のドールが飛び出した。その気配をかぎつけて、補機に群がっていた海棲生物が一斉に振り向く。ルメデルと名付けたこの生物が補機に群がっているのは、DM機関からの排熱に惹かれていると推測されていた。だとすると、補機を回収しようとすれば、抵抗されるに違いない。
ドールのコクピットには、コレペディアと呼ばれるデータベースが組み込まれている。これまでの調査で判明した、この星の生物や資源に関する貴重な資料だ。そのコレペディアの情報が、ルメデルを捉えたモニター映像にオーバーレイ表示される。まずはドールにも匹敵するサイズのこいつらを排除しなければならない。
ナギとイリーナの機体は、先頭に立って突入していった。進路上のルメデルを、斬撃で次々と排除していく。ルメデルの方も二人の機体を敵と認識したようで、次々と群がってきた。そこにダグとラオの機体が、遠距離からの砲撃を加える。調査隊はルメデル相手にずいぶん苦戦させられたようだが、精鋭ドール四機による連係攻撃はこれを易々と駆逐していった。
「──いまのうちにっと」
味方機がルメデルの群れを引きつけているうちに、グインのドールは崖下に回り込みつつ、補機へ接近していった。静音歩行モードで、可能な限り気配を殺しての別行動だ。
「こっちに気づくなよぉ──」
グインの機体は、武装を装備していない。背部にマウントしてあるのは、重力制御装置だ。いずれはこれを応用して、ドール用のフライトパックに転用することも想定されているが、もともとは白鯨船内で人工重力を発生させるためのシステムである。グインの役割は、これを補機に設置することだった。それに成功すれば、補機の巨大な質量が相殺され、ドールでも簡単に運搬できるようになるはずだ。ドール用の追加装備とするには、エネルギー供給の問題があるのだが、補機に直接接続するのであれば、その心配はない。
グインはルメデル群に気づかれることなく補機に到達、接続する作業を開始した。
「グインのヤツ、うまくやっているようですね」
ルメデルの一体を両断しながら、イリーナがナギに語りかけた。もちろん、ナギもその様子はサブモニターで確認している。たとえ戦闘に勝利したところで、補機の回収と運搬が成功しなければ、意味はないのだから。だが、ナギが安堵の言葉を返そうとした時──ドールの制御AIが警戒警報を音声出力した。
「これは──オーバードか!」
警告は、海中からの巨大生物の出現を意味していた。どうやら、ルメデルはこのオーバードの食料だったらしい。全長はドールの数倍はあるだろうか。ルメデルを次々と捕らえては、一口で丸呑みしていく。
「“傲慢なリドル”か──二つ名にふさわしいヤツだな!」
各地で確認されたオーバードには、それぞれ固有の名称が設定されていた。地球人が“なんにでも名前をつけるのが好きな種族”と呼ばれることになる所以である。
「もうちょっと、こっちに気づかないでくれよ──」
機体を降りて、重力制御装置と補機の接続作業を行っていたグインは焦っていた。あと少しで作業は終わるというのに、“傲慢なリドル”がルメデルを捕食するたび、波が発生して頭からずぶ濡れになる。
「オーバードは俺の専門だぜ!」
ダグの機体が、巨大なロケットランチャーをかまえた。彼らアヴァランチ部隊の専用武器として、アームズが開発したものだ。扱いは難しいが、大型生物への殺傷能力を高めてある。素早く狙点をさだめ、ダグがトリガーを引こうとした瞬間、“傲慢なリドル”は意外な行動に出た。頭から呑み込もうとしていたルメデルを、ダグ機に向かって投げつけたのである。
“傲慢なリドル”に高度な知性があるとは思えない。それは単なる気まぐれ──もしくは偶然だったのだろう。だが、結果として投げつけられたルメデルの体は、ダグ機の眼前で、発射されたばかりのロケット弾四発の直撃を受けた。そして、爆発四散した。
至近距離で発生した爆発が、ダグ機とその隣にいたラオ機を吹き飛ばす。
「ダグ! ラオ!」
イリーナが悲痛な声をあげる。
「あ、ああ、なんとかな──」
「ちっ、膝関節をやられた。ここで砲台になるしかねえ──」
ラオ機もダグ機も、それぞれに損傷を受けたようだ。パイロットの生命に別状がないのは喜ばしいが、戦力は大幅に低下した。
「グイン、いま行く! それまで持ちこたえろ!」
「中尉の援護がなくたって、こ、このくらい楽勝ですよ!」
言葉は余裕をよそおっているが、声音は正直だ。グインの言葉には、恐怖がこめられていた。自分よりはるかに大きなルメデルを捕食する“傲慢なリドル”のすぐ横で作業しなければならないのだから、無理もない。だが、ナギの機体もイリーナの機体も、接近戦主体の仕様でチューンされている。目の前のルメデル群を倒さなければ、グインのところへ駆けつけてやることすらできない。
ナギ機に、無数のルメデルが飛びついてきた。押し倒されるような形で、砂浜に倒される。“傲慢なリドル”の出現で、ルメデルもパニックになっているようだ。
「くっ、このままでは──」
サブモニターには、必死に作業を続けるグインの様子が映っている。危険ではあるが、逃げろと命じるわけにもいかない。彼の作業には、NLAの未来がかかっているのだ。
「よし、これで終わりだ!」
そしてついに、グインは作業を終わらせた。補機に接続した重力制御装置を稼働させ、正常に機能していることを確認する。わかりやすく言えば、大荷物に気球をくくりつけて浮かせたような状態だ。これで容易に運搬することができる。
だが、任務は成功させたものの、命を惜しむのなら少しだけ行動が遅れたようだ。ドールの方へ戻ろうと顔をあげた瞬間、“傲慢なリドル”と目があった。グインは理由もなく、動物的直感で悟った。
(こ、こいつ、俺を食う気だ──!)
恐怖で身がすくむ。“傲慢なリドル”の腕が伸ばされてきて、グインは数秒後の自分の死を確認した。だが、恐怖による硬直を打ち破るほど、頼もしい声がヘッドセットから響いてくる。
「グイン──伏せなさい! あとはまかせて!」
それは──その場にいないはずの者の声だった。崖の上に現れた、六体目のドールからの通信である。
深紅の装甲に身を包んだその機体が、崖の上から飛翔する。ナギはその機体の素性に気づいた。
「あれは──研究開発ブロックにあった新型機! Wels.CAIN!」
そして、ナギ以外の者たちも、その場にいた全員が声の主を知っていた。イリーナが涙を浮かべながら叫ぶ。
「生きていたんですね──エルマ大佐!」
深紅のWelsはまるで熟練のアスリートのように宙を舞い、ショルダーマウントに装備されたG-BUSTERをかまえた。
「あなたに恨みはないのだけれど──私たちも生きていかなければならないの、この星で──!」
至近距離からのG-BUSTERの一撃が、“傲慢なリドル”の頭部を粉砕した。
「エルマ、よく来てくれた」
「遅くなってしまってごめんなさい。この機体を整備していたものだから──」
ナギが差し出した右手を、エルマが握り返す。他の者たちにも微笑み返し、抱きついてきたイリーナを受け止めながら、エルマはこれまでの経緯を説明した。
この惑星に落ちる前、エルマはもう一人の青年とともに、異星人の生体兵器群を撃退した。その時の戦いで二人の乗っていたドールは、白鯨の外壁から吹き飛ばされてしまったのだ。だが、その青年が直前にハッチを開き、白鯨の方へエルマの身体をドールの腕で投げつけたのだという。
「あれがなければ、私も船に戻ってこられなかったと思う」
「では、あいつは──」
ナギの言葉に、エルマは目を伏せて、首を振った。
(そうか──。だが、我々全員があいつの行動で救われた。“英雄”だな、あいつは──)
エルマが白鯨に帰還した時、すでに船体は崩壊し、大気圏突入するところだった。手近な区画に潜り込んだエルマは、そのブロックの重力制御装置をフル稼働させて、落着に耐えたのだという。
「降りた後は苦労したわ。凶暴な生物がうようよしているところだったから──」
エルマにとって幸いだったのは、そこが新型ドールや武器を研究開発する区画だったことだ。損傷したドールを修理して乗り込み、エルマは他のクルーを捜して、旅を続けてきたのだという。
「ようやく見つかったと思ったら、まさか戦闘の真っ最中とはね」
「別に偶然じゃねえよ。俺らは招かれざる客だ。ここの本来の住人とは、いつも殺し合ってるようなもんだからな」
ラオが露悪的な言葉を吐き捨てる。彼は彼なりに、原生生物を駆逐しているいまの任務に思うところがあるのだろう。
「──そうね。いずれは殺し合うことなく、彼らとも共存していきたいものね」
エルマの言葉に、一同がうなずく。だが、いつまでも談笑しているわけにはいかない。DM機関の運搬、エルマとともに落下してきた研究開発ブロックの調査、やらなければならないことは、山のようにあるのだから──。
「統合軍を解体する!?」
モーリスは驚いた。ナギの言葉が、正気の沙汰とは思えなかったからだ。そして、それはその場に同席している者たち全員にとって、同様だった。エルマ、ヴァンダム、イリーナ、グイン、ラオ、ダグ──みな、驚きを隠せずにいる。
白鯨の補機や研究開発ブロックの運搬を終え、NLAに組み込むことが成功した、その翌日のことだ。ようやく都市基盤が整ったところで、ナギが言葉の爆弾を炸裂させた。
「今日から俺はナギ准将ではない。お前たちと同じ、無位無官のナギおじさんだ」
「おじさんってお前──そりゃ、ナギおにいさんよりゃマシだが──」
意表をつかれたためか、ヴァンダムの言葉も微妙にズレている。
「どうした? そんなに意外か?」
「意外というか──目的はなに?」
エルマの問いに、ナギは前々から考えていた構想を披露した。
「我々はもはや、地球に帰ることも、ほかの新天地を探すこともできない。この惑星で生きていくしかないのだ。ロビンソン・クルーソーが階級を持っていたか? 新大陸の開拓者たちが部隊編成していたか?」
ヴァンダムは不信げな顔でつぶやく。
「お前まさか、逃げるつもりか? 指揮官やるのが嫌で、軍を解散すると言ってるんじゃ──」
「安心しろ、このNLAにも自治政府を作るべきだ。俺はそこで軍政長官でもやる。自分の義務からは逃げんよ」
「自治政府か──たしかに必要だな。政府首班は選挙で選ぶことになるか──」
モーリスのつぶやきを、その場にいた全員があえて無視した。懐に入れられる利権があるでなし、貧乏くじに近い政府首班など、やりたい人間が勝手にやればいい。
「だが、この星で生きていくため、軍に代わる組織は必要だ。俺はそれをBLADEと名付けようと思う」
「ブレイド──たしか、それって──」
「そうだ、神の言葉を超えた人工的な運命の解放者──その頭の文字をとってブレイド、だ」
かつて、その言葉を唱えたのは、地球種汎移民計画に必要なとある技術を開発した者である。彼はナギの友人であり、ヴァンダムの知己でもあった。
「たしかに、その言葉はこの星で生きていく俺たちにふさわしいな」
「ああ、そしてその司令はお前だ、ヴァンダム」
「俺が司令だと!?」
目を丸くするヴァンダムに向かって、ナギはニヤリと笑った。
「どうした──俺に逃げるつもりかと言った男が、ずいぶんと腰が引けているじゃないか」
「い、いや、階級からいっても、俺よりエルマの方が──」
「階級──もうそんなものに意味はないわ」
エルマは立ち上がり、自分の階級章を床に放り捨てた。
「私はこの星に生きる一人の人間として、ブレイドになる──ヴァンダム司令のもとでね」
「俺ものった!」
「私も!」
エルマの言葉に、一同が同意する。ダグもイリーナも、グインもラオも、それぞれに階級章を投げ捨てる。そして、熱のこもった目でヴァンダムを見つめる。
「ううう──」
「どうした、ヴァンダム。そろそろ腹を決めたらどうだ」
「ううう──わかった、司令でもなんでも引き受けてやる! その代わり、俺の命令に逆らったヤツは腕立て一億回だ! 上腕二頭筋を破壊してやるッ!!」
一同はわきたった。その熱狂が収まったところで、モーリスがおずおずと口を開いた。
「ナギ船長──いや、軍政長官か。実は、私からも提案したいことがあるのだが──」
「ほう、お聞かせいただきましょう」
常に自信に満ちたような表情で弁の立つ人物が、不安そうにも見える顔で提案する。
「ずっと考えていたのだが──この惑星の名前、ミラと名付けてはどうだろう?」
「ミラ──ミラ・トーレスからですか」
モーリスはうなずいた。ミラ・トーレス──その名は、ナギも知っていた。ブレイドという言葉を唱えた人物同様、地球種汎移民計画に尽力していながら、白鯨に乗り込むことがなかった女性。文民と軍人の間を橋渡しした人物でもあり、ナギも彼女の人柄には好感と敬意を抱いていた。
「よいですな──あの方の想いを根付かせたいものです。この惑星ミラに──」
こうして“広くて広くて嫌になっちゃうほど広い地面だも”は、“惑星ミラ”と名付けられた。だが、名付けた種族以外の知性体たちもその名前を共有していくようになるのは、もう少しだけ未来の事である。
ちょうどその頃、NLAから遠く離れたバイアス人の居留地で、保存食が檻のなかでつぶやいていた。
「ああ、はやく誰か、タツをここから出してほしいですも──」
![]()