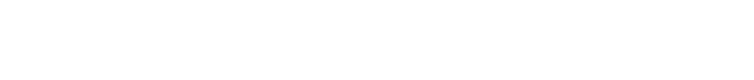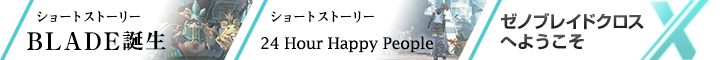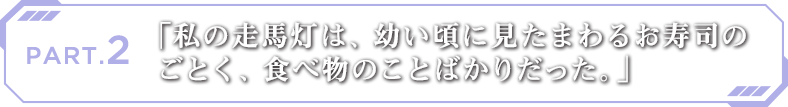死ぬ間際に体験するというこの現象のことは、小説かなにかで読んで知っていた。そこに描かれていたのは一瞬のうちに人生を振り返って涙するという、とても感動的なシーンだった。私も自分がその時を迎えた時のことを思い、しみじみと考え込んだものだ。
しかし、実際はまわるお寿司だった。死を目の前にしてなお、私は食いしん坊だった。
ごめんなさい、なんだかとってもごめんなさい。
私は、自分の人生に何度も頭を下げる気持ちでいっぱいだった。
「頭を下げて、そのまま走れ!」
銃撃の音が響き渡る中、トニーさんの声が聞こえた。途切れ途切れだったのにハッキリと内容が理解できたのは、頭を押さえつけられ、そのまま前に押し出されるといった強制的なアクションとセットになった声だったからだ。
私は言われるまま、テーブルと棚の間を屈んだ姿勢で駆け抜けた。
背後からはトニーさんがついてくる気配がする。
銃を持って現れたゴロツキさんたちは、トニーさんや、ましてや私が標的だったわけではないのだろうか、逃げ出そうとする相手を執拗に追撃することもなく無闇矢鱈に発砲し続けて弾を浪費していた。
銃撃は威嚇? 私たちは命を狙われているのではなく降伏しろとの勧告を受けている?
なんにせよ狙い撃たれて即死ということもなさそうだったので、私は心の中の走馬灯をオフにした。
「リン、君を巻き込みたくない。このまま逃げるんだ!」
「もうじゅうぶん巻き込まれてる気がするんですけど」
「捕まったら二度ともとの生活に戻れなくなるぞ! 襲ってきたのはそういうヤツらなんだ!」
初対面の時の無気力な感じはどこへやら、トニーさんはまるで厳しいしつけをモットーとする父親のように怒鳴った。
「トぉニぃー、まさか逃げるつもりか?」
一瞬、銃撃の音が止んでゴロツキさんのうちの誰かと思われる声が聞こえた。笑い声の混ざったふざけるかのような声だった。
「生きることに執着しないアンタらしくないじゃないか? 外には仲間もいる。無駄に疲れるようなこと、するんじゃねぇよ」
しかしトニーさんは耳を貸さず、姿勢を低くしたまま、私の体を押して前進を促し続ける。いつの間にか、裏口と思しき扉が数歩先のところにまで迫っていた。
「外に出ろ。追手は私が引きつける」
「いえ、それはいいです」
「なにを言っている! 君だけでも――」
「冷静に分析してトニーさんが囮になっても稼げる時間はほんのわずかです。外にもお仲間がいるそうだし、彼らが中から出てきた私を見過ごすなんてこともありえません。つまりトニーさんの提案はこの場合、まったくの無意味になりかねないということです」
一気にまくし立ててから、私はトニーさんを促しつつ裏口の扉に手をかけた。
「ということで一緒に逃げましょう。そしてこのトラブルの理由をちゃんと説明してください」
答えも聞かず、私は扉に体当たりするようにして外に出た。
裏口から出るとそこは巨大な木箱やドラム缶が転がった野ざらしの物置スペースだった。
店内からはまた銃声が聞こえ始めている。でも私たちのことは管轄外だと言わんばかりに無理して追いかけて来るようすもない。
警戒しつつドラム缶の陰から出ようとすると、店の方向とは別の角度から銃弾が飛んできた。店内のゴロツキさんたちと同じくやはり命中率の悪い銃から発射されたものなのか、弾はまるで見当違いの場所に当たって弾けた。身を伏せて視線をめぐらすと、店の入り口方向から数人の男が駆けてくるのが見える。
「なんか段取り悪いなぁ、私たちを本気で捕まえる気があるのかな?」
思わず素直な感想が漏れた。整備部署とはいえ私だってそれなりの期間軍でお世話になっている身なので、こういう場合のセオリーくらいは心得ている。とはいえこっちは丸腰、状況的なイニシアティブはまだ向こう側にあった。
「大通りに出ましょう。ついて来れますよね?」
「あ、あぁ――」
まさか手を引いて行くわけにもいかず、私はトニーさんに合図だけを送り、ドラム缶の陰から駆け出した。
撃ってきた男たちは入口方向から現れたので、露天が並ぶ路地に向かうことはできない。見当外れの射撃をあくまで「注意する」レベルでかわしながら、私は配管などが錯綜する建物同士の隙間に飛び込んだ。
トニーさんがちゃんと付いてきているのを確認しつつ、狭い空間を目一杯の速度で前進する。追っ手の人たちも少し遅れて同じ空間へと駆け込んできたようだったが、跳弾を恐れてか、すぐに撃ってくることはなかった。
障害物の多いルートを、私は地球にいたころ大好きだった遊園地のアトラクションを思い出しながら進み続けた。多分このまま行けばほどなくして大通りへと出ることができる。そうすれば袋小路になることが多い路地よりもかなり逃げやすくなるはずだった。
しかしあとに続くトニーさんの速度は見る見る落ちていった。
「わ――私のことはいいから、やはり君だけでも逃げろ――」
息切れしながら、トニーさんはコミックのサブキャラみたいな台詞を発した。気が付けば追っ手との距離がかなり縮まってきている。
「君に私を助ける理由などないだろ――!」
「私は問答無用で銃を乱射してくる相手に怒っているんです! だからトニーさんを逃がそうとするのは単なる意地、正義感じゃないですからいくら諭すようなことを言っても無駄ですよ!」
へこたれそうなトニーさんを焚きつけるため、あえて怒鳴るくらいの強い言い方で返す。けれどイラついていたのも事実だ。私は、自分が巻き込まれる形になったことを含めて、なによりも理不尽極まりない現状に腹が立っていたのだ。
「気力と体力を振り絞ってください! あともうちょっとです!」
もはや言葉だけでは足りないと思って、私はトニーさんの手を引いた。逃げる速度は格段に落ちてしまうが、こうでもしないとトニーさんは動くことさえやめてしまいそうだったのだ。
距離が縮まったことで目算が効くようになり、追っ手はまた銃を使い出した。追撃にも慣れ、その狙いは正確になってきている。配管に当たり火花をあげて跳ね返った弾が、私の頬をかすめていった。
少しまずいかも――
ここにきてようやく焦る気持ちがわいてきた。しょせん脅しとタカを括っていた銃撃も、距離が近いとさすがに恐怖を感じる。
私はトニーさんの腕を引っこ抜かんばかりの勢いで引っ張り、この狭い空間からの脱出を目指して再び駆け出した。またすぐ近くで跳弾する鋭い音が聞こえる。しかしいちいち警戒もしていられない。モタつきながらもなんとか転倒だけはしないでいるトニーさんを心の中で褒めながら、私は走り続けた。
そしてついに、私たちは大通りの広い空間へと出ることに成功した。
大通りにはそれなりの人通りがあった。
突然飛び出てきた私たちに目を丸くした人もいる。けれど決して広くはない区画に無理やり造られた街では、信じられないようなルートで迷子になる人も少なくない。私たちをそういうタイプだと認識して、大通りの人たちは興味なさそうにして通り過ぎて行く。
さてここからどうしよう――
二手にわかれるという方法もあるし、二人して人波にまぎれるという手もある。悲鳴をあげて助けを求めようか――? いやいや、正式な保護を受けたとしてもいろいろ事情を抱えたトニーさんだからややこしいことになりそうだ。
そんな考えをめぐらしている間にも、追っ手はどんどん追いついてくる。
私はトニーさんの腕を掴んだまま、人波にまぎれるという選択をして駆け出した。
が、目指した人だかりの向こうから、また別の一団が駆けてくるのが見えた。先頭の人が私たちを見つけて指差したりしているので、きっとあれもまた追っ手ということになるのだろう。
ちょっとなめていた。ゴロツキさんたちにもメンツはあるだろうから、段取りは悪くともやはり必死なのだ。それに私たちがそれなりの逃亡を果たしたことでプライドは傷つけられただろうから、もしこのタイミングで捕まってしまえば、ウサ晴らしとして結構な暴力手段に出てくるかもしれない。頭に浮かんだ嫌な考えに、ぶるっと体が震えた。
「もうダメだ――」
情けない声はもちろんトニーさんだ。怒鳴りつけたくなるのを押しとどめ、私はその気持ちを次の行動の起爆剤にした。
大通りの歩道を越えたさらに向こう、一日中渋滞している車道の方向を見る。人波をかき分けて走るよりも、もう一度障害物レースのように車を越えて行くほうが、まだ逃げ切れる公算が大きいような気がした。
私は駆け出す。本日何度目かわからないダッシュ。つんのめるようにしながらも、それでも手を引かれるままにトニーさんも続く。
建物の隅から出てきた追っ手の皆さんと、人波の向こうからやって来た皆さんが合流して、私たちが振り切るべき相手の数は倍になった。つまり追走劇の難度も倍になったということだ。
さすがの私もいいかげん息が切れ、泣きそうな気持ちになってきた。
ガードレールにたどり着き、乗り越えるべく足をかける。勢いのままに車道に出ようとしたその時、通せんぼするかのように一台の大型バイクが停車した。スピードは出ていなかったけれど、私がもう少し早く車道に出ていればちょっとした交通事故になっていたかもしれない。
「オイなんのつもりだ! 危ないだろ!」
バイクの運転手らしき人の声が飛んでくる。女の人の声。あれ――聞き覚えがあるような――
「――――リン?」
名前を呼ばれて、視線を上げる。そこには見知った顔があった。緊張が一気にほぐれ、全身から力が抜ける。辛うじてへたり込むのを耐え、次に発した私の声は壊れた音波兵器のように裏返った。
「うわーん、イリーナさーん! 助けてくださーい!」
アイリッシュバー、フィネガンズ・ウェイク。
私は落ち着いたカウンターで、甘い紅茶を飲んでスコーン(もどき)を食べていた。
休暇で市街へと出てきていたイリーナさんに助けられ、私と、それからトニーさんは追っ手を振り切ることに成功した。バイクに三人乗りという無茶をやっても、本気になれば猛スピードで渋滞をすり抜けることも簡単にできてしまうイリーナさんの運転技術には驚くばかりだ。その後、事情を聞きたいからと案内され、逃げ込むようにたどり着いたのがこの店だった。
「――じゃあまとめるよ。アンタは組織からの借金のために戸籍を奪われて、同じように借金のせいでトンズラした店の主人の代わりにあそこにいた。けれどそこで、また別の組織からの襲撃を受けた。それでいいね」
「はい――。まぁ、そんなところです」
私の隣ではトニーさんがイリーナさんから尋問を受けていた。年齢はイリーナさんのほうがかなり下のはずなのに、縮こまって座っているトニーさんの姿は学校の先生に叱られている生徒のようだった。
「オンボロの店にわざわざ仮の店長か――。居住区画が限られた船の中じゃ、それでも貴重な物件なんだろうな」
「あちこちに手をつけていた借金を一本化する代わりに、名義だけの主人をやれといわれて――」
「ところが一本化なんてのは口先だけ。借金を踏み倒されたヤツらが乗り込んできて、アンタもお尋ね者ってわけか」
ヤレヤレと溜息をついたイリーナさんに、トニーさんは力のない愛想笑いだけを返している。想像したとおり、トニーさんの事情はややこしいもののようだった。
借金やお店の名義など興味のない話題が続くので、私はひたすら紅茶とスコーンに集中していた。対称的にこちらは非常に興味深く、味の真相を探ろうと私は二つ目のスコーンの注文を決心した。
「あのー、すみませーん」
「おいコラ、リン。当事者のお前がなにを優雅にアフタヌーンティー楽しんでんだ」
「だってスコーンが美味しくて――」
まったく、とイリーナさんは大げさにうな垂れる仕草を見せた。
「承知の上でここまで関わったんだろうけど、危機感とか緊張感とか、もう少しどうにかなんないのかよ」
「さすがに大通りで追い詰められたときは泣きそうになりましたよ? でもそこにヒーローが現れて助けてくれたんだから、これはもう全部安心だ、って、そういう気持ちにもなっちゃいますよ」
「ちょっと待て。そのヒーローってのは私のことか?」
「イリーナさん、すごく格好良かったぁ。私には、ドールと同じくらいに輝いて見えました!」
「ドールと同じレベルで褒められてもな。本当にメカと食事にしか興味がねぇんだから――」
「そうですよ、それのなにがいけないんですか? ドールもご飯も、人類にとって欠かすことのできない大事なものです! ――あれ? 大事――大事――――」
「リン?」
「――大っ事なことを忘れていました! 私!」
閃光のようによみがえった記憶に、思わず私は立ちあがった。イリーナさんとトニーさんは突然のことにかなり驚いた様子だった。
「お肉! 私、あのお店にお肉を買いに行ったんですよ! なのになにもかもが空っぽで!」
あそこでしか買えない質の良い合成肉。店長さんはどこかへ逃げたというし、だとしたらあのお肉はもう手に入らないということなのだろうか――?
それは困る!
「トニーさん、元の店長さんの行方を知りませんか?」
「知るわけないよ、私は連れてこられただけだったんだから」
「でも店長さんも借金だらけだったんですよね? 同じように借金だらけだったトニーさんなら、そういう人が流れ着く先というか、末路というか――いろいろ想像がつくんじゃないですか?」
「末路って――」
「リン。お前、結構ひどいこと言ってるぞ」
表情を引きつらせたトニーさんを受けて、イリーナさんも苦笑いで私を見た。もしかするとすごく失礼なことをしたのかもしれないが、今はお肉のことが最優先、謝るのはあとにしよう。
「まぁうわさ程度なら逃亡先のあてがないこともないけど、きっとすでに組織の手もまわってるはずだ」
「じゃあ急がないと! お肉が幻になってしまいます! 店長さんの合成技術は店長さんしか知らない秘伝中の秘伝なんですから!」
立ったまま残った紅茶を飲み干し、それを行儀が悪かったと反省する間もなく、私は荷物を抱えて簡単な身支度を整えた。
「案内してください、トニーさん!」
「え――」
「おいおい、せっかく逃げ切ったのにまた危ないところに飛び込むつもりか?」
「もちろんです!」
戸惑うトニーさん、呆れた顔のイリーナさんに向かい、私は胸を張る。
「お肉のためなら、私はブラックホールにだって飛び込んで行きますよ!」
![]()