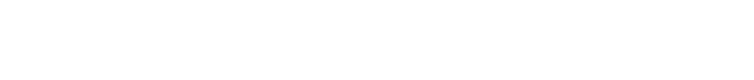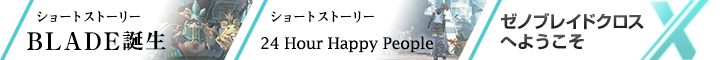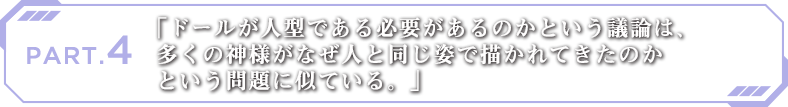人智を超えたものを理解しようとするとき、人の形を手がかりにできるのであればその敷居は下がる。神様に人と同じ表情があるからこそ宗教画は感動的であり、ドールに手足があるからこそ人はこの複雑な乗り物を乗りこなすことができるのだ。まさにドールとはよく言ったもので、彼らは人のわがままなニーズに応えてくれる素直な隣人に他ならない。
だが、いま私の目の前では一体のドールが厄介者扱いされ、いい大人二人がその撤去作業の責任を押し付け合い言い争っていた。
知らぬ間に持ち場を離れて仕事をエスケープしようとした末に勝手に事故ったドールの撤去など知ったことではない――これは拡張工事を取り仕切っていた現場監督の主張。
現場で働いていた人間が起こした問題なんだからこっちの敷地内だろうとなんだろうと撤去はそっちが行うべき――これは店を半分吹き飛ばされたカフェの店長の主張。
平行線をたどる論戦の原因は、カフェのすぐ隣の工事現場から転がり落ち、店の敷地内で稼動不能になった作業用ドールにあった。ドールに乗っていた当人はすでに病院へと送られ、さて動かなくなったドールを誰が片付けるのかと問題になったとき、対立ははじまったのである。
普通に考えれば現場監督が全責任を負うべきなのだろう。しかしハシエンダでは少し事情が異なるようだった。そもそも拡張工事自体が正規に発注されたようなものではなかった。現場監督を名乗る人物が自発的に――というか勝手に工事をはじめ、それによって得られた空間を売り出すつもりでいたらしいのだ。そして事故ったドールの持ち主も現場監督に雇われたわけではなく、売り上げが出たあかつきにはいくばくかの分け前を得ようとして、やはり勝手に手伝っていただけだという。だから現場監督に管理責任はない、ということになるのだ。
ツッコミどころが満載で、現場監督の話をすべて信じていいものかどうかもあやしいものだが、それがハシエンダでの常識であるらしい。義務とか契約とか、そういうもので痛い目を見てきた人たちが集まる場所だからこそのメチャクチャな常識だった。
敷地内に落ちてきたことを不運と思ってあきらめるんだな、と、ついにはそんな身勝手なことまで口にし出す現場監督。さすがにカフェの店長もキレて、相手の胸倉に掴みかかって行った。その店長の手には光るものがある。あれは、確かサンドイッチを切るときに使うパン切りナイフ――
咄嗟に駆け出し、私は店長の腰に飛びかかってその動きを止めた。私と同じく成り行きを見守っていたトニーさんもタイミングよく動いてくれて、店長と現場監督の間に両腕を広げて割って入る。
「ダメです! それはお料理に使うもので人を傷つける武器じゃありません!」
しかしカフェの店長さんは、ここで引き下がったら示しがつかないとか俺の縄張りで言いたいことを言わしたままではいられないとか、せこいマフィアみたいなことを言い出して聞く耳を持ってくれない。
「ドールが問題なんだったら、私がなんとか動かしてみますからぁ!」
力いっぱい叫ぶと、ピタリと店長の動きが止まった。突然のことだったので少しつんのめってから、私は店長の顔を見上げる。
本当か? と店長が聞いて、それに続いて対峙していた現場監督も、お嬢ちゃんにできるのかい? と聞いてきた。
「とりあえず動けるようにしてこの場から移動させるくらいなら、多分、すぐにでも――」
ほう、そりゃ助かる! と、今度はカフェの店長と現場監督の声が重なった。ついさっきまでの剣呑な雰囲気はどこへやら、二人してニコニコとした顔を私に向けてくる。厄介ごとが都合よく一掃されたとばかりに、その表情はビックリするくらい清々しかった。
いやー機体を引き取らせるにしても持ち主も面倒くさそうなヤツらだったんで本当にありがたい――と、これは現場監督。聞けば件の作業用ドールにはいろいろおかしな改造が施されていて、転売してしまおうにも買い手がつきそうにないとのことだった。
「おかしな改造――?」
なんとそのドールは、ハシエンダで不定期に開催されているドール同士の格闘競技会に出場するために、およそ現場作業には向かないピーキーな改造がなされていたというのだ。そんな競技会が開かれていることも驚きだったが、それよりも私にとって驚きだったのは――
「へぇ、チャンピオンになると賞品がもらえるんですか。ちなみにその賞品っていうのは――――えぇっ!? あの最高級合成肉の、フェイクマツサカなんですか!?」
見立てどおり、ドールの損傷はそれほどシビアなものではなかった。
自立稼動できるようにするにもたいして手間取ることはなく、ほどなくして、私はカフェの敷地内からドールを移動させることに成功した。
そのドールは軍でも採用されているFormula系の流れを組みつつも、酔狂なオーナーを渡り歩いたせいかフレームレベルからかなり手を加えられていて、現在は腕部がかなり肥大化したゴリラのような姿をしていた。見た目はものすごく力仕事に向いてそうに見える。だからこそ拡張工事の現場に参加することを認められていたのだろうが、調べてみれば腕は打撃力を向上させるためにウエイトが増加されているだけであって、それに対するバランスの調整などは一切無視されていた。そんな機体で工事現場などに立てば、転がり落ちてしまうのも当然のこと、事故は起こるべくして起こったのだ。
私は、やっと見つけたわずかばかりの空き地にドールを落ち着かせて、コクピットから各部のチェックを行う。改造の具合はひどいものだったけれど、メンテナンスはそこそこ行き届いていたようで、修理を完全なものにするのにパーツレベルでの交換が必要な箇所はとりあえず見当たらなかった。
「本気なのかい? リン」
外からトニーさんの声が聞こえた。私は作業の手を止めずに、開放型のコクピットの出入り口に向かって声を返す。
「もちろんです。そうじゃなきゃ、ここに何時間も引きこもったりしていませんよ」
トニーさんの質問は、私がついさっき下した決定への再確認――私は、ハシエンダではボトミングと呼ばれる格闘競技会に出場することを決めていたのだ。
もちろん目的は、賞品である最高級合成肉の獲得である。
ネット経由でエントリー手続きをすでに完了したあと、私は事故ったドールを入院中の持ち主から借り受けた。修理費用と撤去にかかる手間賃をまける代わりにレンタル代金はタダ。しかし実は当人も無茶な改造を重ねた機体を持て余していたようで、名目上はレンタルでも、実質その機体は私が引き取るような形になった。なので、ドールを好き勝手にいじくりまわしても文句を言われることはない。一気にボトミング出場へのテンションが高まり、ワクワクしながら機体チェックをはじめたのが今の私である。
「しかし――やっぱり無茶だよ」
「もはや完全に手がかりを失ってしまったお肉屋さんの店長の行方を追うよりも、こっちの方がお肉ゲットの近道です。なんてったって、私はドールの専門家なんですから!」
私の勝利宣言に対し、微妙な沈黙ができる。
やがて返ってきたのはトニーさんの溜息だった。
「やれやれ――さすがだよ」
トニーさんは、どっこいしょとコクピット前のバンパーの上に腰掛けた。
「ポジティブというかあきらめが悪いというか――まぁ、あきらめが悪いのだけは私も同じか」
コクピットの中からのぞき見ると、トニーさんの目は寂しそうに遠くを見ていた。そういう同情を誘うような仕草を見るのは好きじゃない。でもトニーさんの場合、それは意図的なものではなく今やクセのようになっているものなので、そうなるまで繰り返されたであろう背景のことを思うと、少しの切なさが胸を締め付けた。
「そういえば――トニーさんはドールの操縦ってできますか?」
「ドールの操縦? ホビー用のものになら乗ったことはあるけど」
「それはいつのことですか?」
「もう五、六年前になるかな」
「なるほど。では、ボトミングの当日までに勘を取り戻すべく練習しておいてください」
「え――? いやちょっと待て、私に出場しろって言うのか!?」
身を乗り出して、トニーさんはコクピットを覗き込んできた。
「ボトミングっていうのはつまり、ゼロ距離で組み合ったドール同士の殴り合いです。そこで重要視されるのがパイロットとコンビを組むセコンドの存在で、離れた位置から状況を見渡し指示を与えるその技量次第で、ボトミングの勝敗は決すると言っていいでしょう」
つまり――と、言葉を続けようとして、私はトニーさんの顔を見た。その表情は悪い予感を感じてか引きつっていた。
「トニーさんに私以上の状況判断と指示が期待できるとは思えません。ならばセコンドには私、パイロットにはトニーさんがなるしかないというわけです」
「しかし――なら別のパイロットを探すほうが得策なんじゃ――」
お得意の「しかし」という言葉を発して、トニーさんは視線をそらした。そんなトニーさんを私は真剣な目で見つめる。
「トニーさん、私は立ち直るのに焦る必要はないと言いました。でも、自棄(やけ)になって怠惰な生活を続けるトニーさんのことも私は心配なんです。だから――自棄はいっそのこと、ここで発散しちゃいませんか? 全部出し切って自棄を一度終わらせましょうよ!」
「リン――」
背けられていた視線がまた私のほうに戻ってくる。説得しようとするほどおこがましい気持ちはなかった。でも、言いたいことが伝わってくれれば嬉しいとも思っていた。これでトニーさんの抱える重たい気持ちが晴らせるわけではない。それでも、私はトニーさんにきっかけをつかんで欲しかった。再び、生きることに一生懸命になれるきっかけを――
「わかった。どうせ無駄遣いしていた命だ。死ぬ気でやるよ」
力なく、つぶやくようだったトニーさんに私は首を振る。
「そうじゃないですよ、トニーさん。よく言われる死ぬ気になれば何でもできるってアレは嘘です。人は、生きる気だから無茶ができるんですよ!」
私の言葉に、トニーさんが吹き出す。
笑い声をまじえながら、トニーさんはもう一度わかった、と言った。
ドールの修理、および改造は自分でも驚くくらいの急ピッチで進行した。
私は実作業に集中し細かい部品の調達などはトニーさんに任せていたのだが、ハシエンダに住む人たちはみんなお祭り好きのようで、私たちが何か面白いことをしようとしていると聞きつけると、昼夜を問わず次から次へと使わなくなった機械などを持って現れた。
数日も経てば、私たちの作業場はちょっとしたコミュニティを形成するに至った。それは学校のクラブ活動のようでもあり、ずっと終わらないパーティを続けているようなものでもあった。そこはすごく居心地が良くて、私はハシエンダのみんなとたくさんお喋りをして、笑いながら一緒に食事をして、そしてひたすら作業に没頭することができた。
その間、もちろん基地に連絡は入れていたけれど、非合法の場所でなにをやってるんだとよくない噂の一つもたてられていたかもしれない。
しかし、すべてはお肉のため。賞品を得るまでは、私も帰るわけにはいかないのだ。
毎日やって来る人の中には、対戦相手、つまり現チャンピオンの情報を持ってきてくれる人もいた。
相手が操る機体は通称クラブマンと呼ばれるやはり建築現場用のドールを改造したもので、かなりの重量級ということだった。対戦が行われるフィールドの面積は狭いので、ボトミングにおいて運動性はあまり重要視されない。組み合って、そこからの力比べの果てに相手を行動不能にすれば勝利となるのだから、機体重量のインフレは必然的なことだった。そんな中であえて重量級と言われるクラブマンは、きっと恐竜的な進化を成し遂げた機体であるのだろう。それを裏付けるようにクラブマンの常勝伝説はハシエンダの誰もが知るところであり、本来は十回連続で勝ち抜かなければ優勝できないボトミングのルールも、今やその不動のチャンピオンを一度でも倒せば即優勝、ということに変更されているらしい。優勝賞品がお肉になった経緯も、あまりにも勝利を重ねるチャンピオンが、品目のマンネリ化に異議を唱えた結果だということだ。
かくして私の対戦相手に対する印象は、巨漢の食いしん坊、ということで固定された。ならば同じ食いしん坊である私としても負けるわけにはいかない。
たくさんの人たちの協力もあってドールの改造はますます快調に進み、予定していたスケジュールをかなり短縮して作業は終了した。
そして迎えたお披露目の日。
完成した機体に、私はニューオーダーという名前をつけた。
機体さえ仕上がってしまえば時間をおく必要もない。私は早速クラブマンのチームにボトミングの開始に同意せよとの通知を送った。このいわゆる挑戦状の送付のタイミングは挑戦者の自由であり、チャンピオンが同意すればその日のうちにボトミングは開催されるのだ。
ほどなくしてチャンピオンから同意する旨の返事がくると、私はみんなと一緒にパレードのようにしてニューオーダーを対戦会場へと移動させた。
会場はハシエンダの中心部にあった。
本来は資材置き場に使われるべき空き地だということだったが、その空間は鋼鉄製の柵で仕切られ外郭には客席らしきものまで設けられている。すでに見物人は多数押し寄せてきていて、怒号や歓声が飛び交う中、私たちは挑戦者側のコーナーに機体を待機させた。
見ると、対するチャンピオンコーナーにはクラブマンの姿もあった。柵越しなのでよくは確認できないものの、いびつな恐竜的シルエットを描いていた私の想像はまるで的外れというわけでもなさそうだった。
ステップを使ってニューオーダーのコクピットによじ登り、私は中に収まったトニーさんに話しかける。
「緊張してますか? トニーさん」
「そりゃあ、ね」
「大丈夫ですよ。初手さえ上手くいけば、勝てます。パワーはともかく機体バランスはこっちのほうが上なんですから!」
「――うん、まぁなんとかやってみるよ。こっちにはリンが用意してくれた必殺技もあることだしね」
「え? ああ、アレですか。アレは私のロマンみたいなものですから、過度に期待されても困るんですけど――」
と、そこでセコンドアウトのサイレンが鳴り響いた。私は言葉を切り、手でグッドラックの合図をしてコクピットから降りようとした。すると、そこにトニーさんが声をかけてくる。
「リン――!」
「はい?」
ステップの途中で足を止めて、私はトニーさんを見上げる。トニーさんはコクピットから身を乗り出して、私を見下ろしていた。
「地球で別れた私の娘は、君と同じくらいの年だったんだ。だからってその姿を投影するつもりはないけれど――君の言葉は私に力をくれる気がする!」
あえてこのタイミングで発せられたトニーさんの言葉は、もしかすると押し付けがましかったのかもしれない。でも私には真っ直ぐなものが伝わってきて、不思議と、なにか満たされるような気持ちが心にわきあがった。
「そういうふうに言われるのは嬉しいですよ、トニーさん」
「感謝しているよ、リン」
言い終わると、トニーさんはコクピットの奥へと姿を消した。私もステップを降りきって、地面に足をつける。同時にニューオーダーは動き出し、フィールドの中央へと移動をはじめた。その背中を見送り、私はトニーさんの言葉を反芻した。
君の言葉は私に力をくれる――
そうか。
もしかすると人って、ただご飯を食べてるだけじゃちゃんと生きていけないのかもしれませんね、トニーさん。
![]()