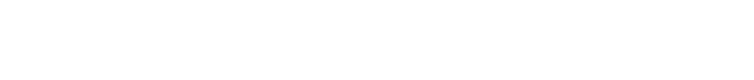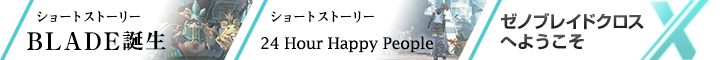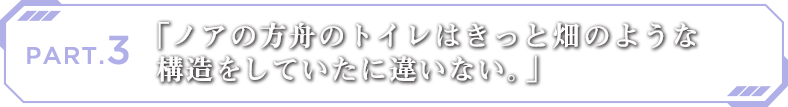そこでは人工的に食物連鎖が再現される必要があっただろうから。
同じ思想のもと、宇宙の方舟である『白鯨』内の畑は工場のような造りになっていた。発達した生物工学の実践の場となった畑から、野菜だけではなく、肉や魚までもが合成されて出荷されてゆくのだ。
当然、公的な畑(プラント)は当局によって運営されていて、食物の供給は厳重に管理されていた。しかし先の解釈で言うなら、今や畑は試験管の中にだってつくることができる。当局の目が行き届かない違法な畑は無数に生まれ、それはいつしか慢性的な食材不足に陥っていた船内社会の必要悪となり、黙認されるようになった。
試験管の中の極少なものから地下の倉庫を改造してつくられた大規模なものまで――それら違法な畑は身も蓋も無くファクトリーなどと呼ばれていた。
私がトニーさんと一緒にやって来たファクトリーは市街区画にある中でも最大規模のもので、『ハシエンダ』の通称を持っていた。
私にしたっていつも真面目にプラントから出荷されてくる食材ばかりを使っているわけではないが、正規品でないものはすべてフィッシャーマンズ・アレイで手に入れていたので、直接ファクトリーを訪れるのは初めてだった。
トニーさんのあとに続いて私はハシエンダの奥へと向かって歩いて行く。かつて同じ工事現場で働いていた仲間に聞いただけというわりに、トニーさんの道案内は完璧に近かった。案外、もとはやり手の人物だったのかもしれない。抜け目のない記憶力に、私は軍の中でも高い地位にある人と同じ雰囲気を感じ始めていた。
「私はあの店の店長のことはまるで知らないんだけれど、こういう場所で居心地の悪さを感じない人だったのかな?」
「え? うーん――」
ふいに立ち止まって振り返ったトニーさんに、私は首をひねって見せた。
市街地区の地下に張り巡らされたライフラインのメンテナンススペースを利用する形で、ハシエンダという空間は形成されていた。地下にこんな空間が、と驚くほどの広さがあり、また照明に関しても地上とほぼ変わらない光量が確保されているので、息苦しさや陰鬱さを感じたりするようなことはない。しかしトニーさんが言った居心地の悪さとは、きっとそういった最低限の環境のことでなく、もっと情操的な――要するに壁にケバケバしく描かれたグラフィックや、そこかしこから聴こえてくる大音量の音楽に馴染むことができない気持ちのことだ。ハシエンダは、まるで巨大な地下クラブといったおもむきだった。
私だってそういった雰囲気は苦手だ。音楽とともにときどき聞こえてくる若者たち(といっても私よりいくつか年上なのだろうけれど)の奇声には、どこか悪魔的なものを想起させられて恐怖を覚える。私が訪れるといつも快活な笑顔を返してくれていたお肉屋さんのおじさんが、果たしてこの雰囲気の中でくつろいでいるのかと問われれば、それは首をひねって返すしかない。
「とはいえ逃亡先なわけですから、居心地の良さなんて贅沢は言ってられないはずです」
「それはそうなんだけど、私でさえ場違いなんだから肉屋のおじさんはもっと目立つんじゃないのかなぁ」
「忘れてませんか。ここはあくまでファクトリー、肉も野菜もとれる畑なんですよ。お肉の合成技術を持ったおじさんの再就職先としては充分すぎる場所でもあるはずです」
「しかしなぁ――」
「もう! なんだかんだ言って面倒くさくなってきただけなんじゃないですか? いいですよ! ここまで来れば私一人でも何とかなりますし、トニーさんは地上に戻ってください! ありがとうございました!」
頭を下げ、トニーさんの顔を見ることもなく背を向けて、私はハシエンダのさらに奥へと向かう階段を降りはじめた。少しイラついてしまったのは、疑問や否定ばかりが先行するトニーさん独特の言い回しがたまたま繰り返される形になったから。なんだかここまでやって来た私のことを軽率だと非難されたように感じてしまったのだ。そんなことは、わざわざ口に出して言われずとも自覚くらいしている。
逡巡があったのかわずかな間をおいたあと、やがてトニーさんは私を追いかけて来た。
「困るよ、リン――。君のことはイリーナさんからくれぐれもよろしく頼むと言われてるんだ。それに戻ったって私も追われている身だし――――おぉい、待ってくれよリン!」
最後には泣きそうになったその声に、私は心の中で溜息をついて、階段を下りるスピードを少しだけ緩めた。
見て回れば回るほどハシエンダは不思議な場所だった。
化学的な合成を行うための素材や触媒で満たされたタンクが林立し、それらをつなぐパイプラインが縦横無尽に走るようすはファクトリーの名に恥じぬ工業的な風景だといえた。でも実際に合成を行う施設や出来上がった食材を保管しておく冷蔵庫などは目立たない場所に追いやられ、空間のほとんどは、たむろして談笑する人たちや地面に布を広げただけの怪しい露天商、ドラム缶を叩いたり見たこともない機材で自分の声を拡声するストリートミュージシャンなどの姿で埋め尽くされていた。
工業地帯のスラム街――ハシエンダを何かに例えるとなると、それがいちばん適切かもしれない。退廃的でありつつもエネルギーが感じられ、無法でありつつも同族意識に基づいたルールも感じられる。そしてなにより畑でありつつも居住空間として多くの人間を飲み込んでいるという不思議な共存。それがハシエンダであり、だからこそここには、他にはない麻薬的な魅力が詰まっているように思われた。
ハシエンダの片隅にあるひっそりとしたカフェで、私とトニーさんは休憩をとっていた。ひっそりと言っても音楽や人の嬌声があまり聞こえてこない外れにあるというだけで、設備の拡張工事を続ける騒音が辺りには響き渡っている。ハシエンダは今も、急速にその敷地を広げ続けているのだ。
「ドールの駆動音もしますね? きっと正式なメンテナンスも受けられない未登録機のはずなのに、よく稼動してるなぁ」
「そういえば、リンは軍の整備班所属なんだっけ」
「はい。だから諜報活動は専門外、苦手なんです」
油が大量に混ぜられた粘っこいアイスクリームをもてあそびつつ、私の口からは自然と溜息が漏れた。ここ数時間、刑事ドラマのようにたくさんの人に聞き込みをしたけれど、姿を消してしまった店長の行方は、その手がかりさえつかめなかった。やはりうわさ程度の情報だけを頼りにたった一人の人間に捜しだそうとするのは無理があったのだろうか。本職の諜報部員だってもう少し下準備を整えてから行動するはずなのに、私は店長のフルネームさえ知らないのだ。
「これだけ捜してもダメだったんだ、そろそろあきらめ時なんじゃないかな。地上じゃもう夜中の時間帯だろ?」
「え、もうそんなになります? あちこちに集まっている人がずっとおんなじ調子なんで、全然わかりませんでした」
「ファクトリーはどこも、二十四時間休まずに稼動、が基本だからね。とくにハシエンダは芸術家気取りの奇妙な連中が多く集まっているから、余計に時間の概念などは毛嫌いされるんだよ。今や時間は星の動きではなく船のメインコンピューターに支配されるものだから、時間に対して頓着しないことこそが、システムに対抗し、自由を勝ち取ることだと考えられているんだろう」
「なんですかそれ。ヒッピーですか?」
「ずいぶん古いことを知ってるんだね」
「そうでもないですよ。何度目かのリバイバルでちょっと前にも流行りましたし。――なるほど、そう考えるとここの異様な空気にも納得できる気がします。どこか現実離れしてるんですよ、ハシエンダって」
「現実離れか――そりゃあいい」
トニーさんは自嘲気味に、悪い言い方をするとカッコつけた笑い方をして見せた。その芝居がかった仕草は出会ったときから一貫していて、銃撃戦や逃亡の際に見せた情けないようすも、今から思えばまた同じだった。私にはそれが何かを隠すためのものに見えて仕方がない。
「トニーさんは、どうしてそんな――戸籍を売らなきゃいけないような借金をしたんですか?」
「え――?」
それはずっと気になっていたことだった。立ち入った質問なのは承知していたので、トニーさんが少しでも答えにくそうにしたら、それ以上聞くつもりはなかった。でも、トニーさんは私の問いに穏やかに笑って返してくれた。その笑顔もやはり芝居がかって見えたけれど、それでいてこれまでとは少し違った印象があるようにも感じられた。
「私はこれでも、人の生命維持についてそれなりの論文を提出したこともある研究者だったんだ。少し探せば『白鯨』の中にも研究成果を利用した装置もあるはずだ。それなりの成功をおさめていたんだよ、私は――」
ふいに言葉を切って、トニーさんは私から顔を背けた。遠くを見つめて、その目がゆったりと目を細められる。
「けれど私は研究に没頭するあまり家族を顧みず、奥さんとは別れてしまった。たった一人の娘とも自由に会えなくなって、私の戸籍は一人ぼっちになった」
「それが戸籍を大切にしなくなった理由なんですか?」
「厳密に言うとちょっと違うかな。私はいつかまた三人で暮らせる日が来ると信じていたからむしろ戸籍は大切だった。それは家族を証明するものだからね。しかし、離婚が成立した数ヵ月後に起こったのがあの事件だ。地球が異星文明同士の戦いに巻き込まれ、人類が宇宙へと逃亡せざるを得なくなったあの事件――」
トニーさんの声が沈んだ。そして私も、そこまで聞けば察するところもある。
実績のある研究者であるトニーさんには、恐らく優先的に『白鯨』に搭乗する権利が与えられていたはずだ。もちろん時の政府らは全人類の宇宙への脱出を約束していたけれど、人類生存の可能性を少しでも高めようとするならばそこに序列があったのは明白で、トニーさんはいわば選ばれた側の人間だったのだろう。そしてこの優先権を少し悪用すれば本人の家族にも搭乗の権利を与えることも可能で、そういう裏ワザが横行したのも公然の事実だ。つまり普通なら、トニーさんの家族も問題なく『白鯨』に乗り込むことができていたはずだったのだ。数ヶ月前に離婚が成立してさえいなければ――。
「『白鯨』のメインデータの中に妻と娘の名前は登録されていなかったが、私はあらゆる可能性を信じて船の中を捜し回った。しかし、二人は発見できなかった。他の移民船に乗ったことも充分に考えられるが、『白鯨』のように生き残った船が一体いくつあるものか――」
『白鯨』に家族が乗っていないことを知ったその日より、トニーさんにとって戸籍は疎ましいものとなってしまった。それは家族を救う命綱になるものだったのに、効力を発揮する前に千切れていたのだから。八つ当たりするように、借金のカタに売り飛ばそうとする気持ちもわからなくはない。
「じゃあトニーさんの借金は、家族を捜す費用のために――?」
「いや――。確かにそのために使ったものもあるが、ほとんどは自棄になって荒れた生活を続けてきた代償だよ。浪費と怠惰がすっかり板についてしまった。立ち直ることを放棄すれば、気持ちはいくらか楽になったからね」
「つらい話ですね――」
「違うよ。ただただ情けない話さ」
相変わらず工事の騒音がうるさく響く中、私のアイスはもてあそんでいるうちにすっかり溶けてしまっていた。ドロドロのマーブル模様が、今の私の気持ちを表しているかのようだった。
「でも――トニーさん。誤解を恐れずに言うと、トニーさんはまだ立ち直らなくてもいいと思います」
?と、トニーさんは遠くを見るのをやめて、私を見た。
「もちろんトニーさん一人の生命維持にかかる船内設備の稼動費用などがしばらく無駄になるので、その辺は本当にもう全面的に申し訳なく思ってほしいんですが――。それでも、すぐには立ち直らなくていいです。だってそれは、家族のことをあきらめちゃうということですから――」
「リン――」
トニーさんは目をパチクリさせている。それでもいつものように「いや」だとか「しかし」などの言葉がすぐに返ってこないので、私は自分の言葉を続けた。
「立ち直らず、思いっきり引きずって、だけど一生懸命生きてください。立ち直ることはいつでもできます。ゆっくり待って、その気力が出てきたときにあらためて試してください」
じっと見つめているトニーさんに、私は素直な気持ちで微笑んで返した。
「効率の悪さは人間らしさです。焦らずにいきましょう!」
トニーさんはビックリしたような顔のまま、まじまじと私を見つめている。
その表情を目の当たりにして、私はハッと我に返った。後悔の念が押し寄せ、背筋がサッと寒くなる。
しまった、いま絶対「いいこと言ったでしょ、私」って顔になってた!ドールの教習所の先生の受け売りなのに、しかも相手は立派な大人なのに、ものすごくエラそうな感じになってしまった。
私ってばいつもこうだ。口に出してしまってその直後に心の中で後悔する。人に助言めいたことを言う前に、まずこのダイレクトな脳内言語化スピーカーをなんとかしなくちゃいけないのだ、私は。
「リン――」
「うああぁぁ、ごめんなさい、生意気なこと言って! トニーさんの気持ちもまったく考えないで、自分で実践したこともない理屈をだらだらと――」
「いや、そうじゃなくて――」
パニクる私に、なぜかトニーさんのほうが恐縮したようすで身を乗り出した。
しかし私の混乱は止まらない。顔の前で両手を振って、ひたすら頭を下げ続ける。
その時――
ふわっとカフェのテーブルが浮き上がった。
最初はトニーさんが不安定に手をついたせいだと思った。
しかし違った。
続いて椅子が地面を転がり、簡単に建てられただけのカフェスタンドも大きく傾いた。
「なにが――」との疑問の声をあげる間もなく、続いて押し寄せたのは激しい破壊音。先ほどまでの工事の騒音など比べ物にならないくらいの立体音響が鼓膜をつんざく。
カフェにあったすべてが、一瞬にして吹き飛ばされた。
椅子ごと地面に放り出された私は、慌てて頭をかばった。爆発音は聞こえなかったので爆弾の類が炸裂したということはないと思ったが、なにかが崩落したのなら、落下してくるガレキに対して備えなければならない。
しかしパラパラと落ちてきたのは埃だけだった。
私はむせ返りながら少しの間ようすをうかがい、やがてゆっくりと体を起こした。
隣には同じように埃まみれのトニーさん。命は無事らしい。
周りの状況はといえばひっくり返ったテーブルや椅子に、傾いたスタンド。そして――
「っ!?」
目の前に横たわる巨体に、私は飛び跳ねて驚いた。
鈍く光る油まみれのシャフト、いまだ稼動を続けるモーター音、余剰エネルギーが転化されたことによって発生した熱風。
暴力的なまでの機械の塊が、うずくまっていた。
それは、見たこともない姿をした一体のドールだった。
![]()