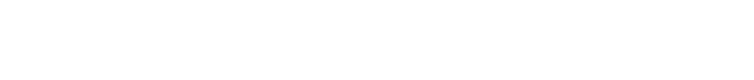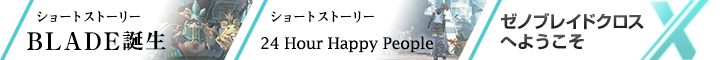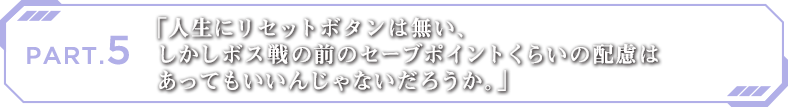勝負に負けたとしても経験は残り、新たな人生を戦うチャンスは与えられて当然だと、私は思う。
どれだけ積み重ねることができたのかが最終的な勝負の行方を左右する──
果たして不動のチャンピオンの経験に匹敵する準備を整えることができたのかと、私は自問した。
ボトミングの会場となった広場の中心では、トニーさんの駆るニューオーダーと、チャンピオンのクラブマンが鼻先で対峙していた。観客席の最前列、お立ち台のようになった小さな場所で、私はインカム越しにトニーさんの荒い息遣いを聞いていた。緊張感が少なからず伝染してくる。景気の良い言葉で送り出したものの、私にもまったく不安が無かったわけではないのだ。
行儀の悪い観客たちの怒号が続くなか、音の割れたブザーが鳴り響く。
試合開始の合図だ。
観客たちはさらに盛り上がり、怒号は歓声となって会場全体を包み込む。
だが、ニューオーダーはすぐに動かなかった。
まさかいきなり動作不良? いや、つい先ほどまで駆動系はいい音を鳴らしていた。その可能性は低い。それよりもまず疑わなければならないのは、ドールの扱いに慣れていないトニーさん自身のミスだ。
「トニーさん!」
インカムのマイクに力いっぱい叫ぶ。
よもやあれだけ練習を繰り返した操縦の段取りを忘れたわけではないだろう。トニーさんは多分、雰囲気に呑まれてしまっているのだ。
私の怒鳴り声からさらにワンテンポ遅れて、ようやくニューオーダーは動き出した。
しかし、それはあきらかに遅すぎた。
巨体に似合わぬ敏捷性を発揮して、クラブマンはもとから低い重心をさらに低くしてニューオーダーのふところにもぐり込んだ。クラブマンの名前の由来となったハサミ状の腕が滑らかに動き、ニューオーダーの脚をすくいにかかる。
それを避けられないのは、トニーさんの操縦技術が未熟なせいではない。ジャンプしたり片足を上げたり、とっさの回避運動においてそんなアクロバティックなモーションが可能なのは軍用のドールくらいだ。操縦レベルや機体スペックがどうこうではなく、必要性の問題である。
脚部をなぎ払われ、バランスを崩したニューオーダーの機体が傾く。
するとすぐさま片方の腕が反応し、末端肥大の巨大な「手」が地面につき、かろうじて転倒は回避された。人間の動きをトレースした見事な操縦のようにも見えるが、それはオートで起動する姿勢制御の付加機能が働いたに過ぎない。操縦技術の錬度が問われるのは、むしろそのあとの対応──いかに早く体勢を立て直し、次なる行動に備えることができるのか。しかしトニーさんは、ここでも遅れを取った。
低くした体を起こすのと同時に突進を開始するクラブマン。
ニューオーダーは無防備なままで体当たりを食らわされてしまった。
地面に深く突き立てられた巨大な腕のおかげで弾き飛ばされることは免れたものの、与えられた衝撃の激しさにニューオーダーの体がガクガクと揺れる。インカムを通じてトニーさんの悲鳴が聞こえた。
「耐えてください、トニーさん! 相手の動きに注意して!」
とは言ったものの、開放型とはいえ狭いコクピットからの視野は極端に狭い。あれだけ機敏に動かれてしまっては相手を目で追いかけることだけでも至難の業のはずだ。だからこそセコンドがいるのだが、私だってその役回りを担当するのは初めてである。トニーさんの反射神経が相手の動きについていけないように、私の思考の反射神経もまたボトミングという競技のスピードに慣れてはいない。結果、「注意しろ」などという曖昧な指示しか出すことができなかった。
すぐに反撃がこないと見るや、クラブマンは二本の腕を同時に操ってニューオーダーに組み付いてきた。ボトミングにおける試合運びの定石である力比べに持ち込もうというのだ。意外性のある戦い方ではないけれど、王道を確実にやってのけるからこそ、きっとこのチャンピオンは常勝でいられるのだ。
「止まっちゃダメです! 動いて!」
『動くって──どんな風に!』
返ってきたトニーさんの声は震えていた。私は必死に頭を回転させる。今のトニーさんに必要なのは工学的な理屈じゃない。もっと感覚的で明確な、それこそボクシングの試合のセコンドのような指示だ。
「身じろぎするだけでもいいんです。とにかく相手の有利な体勢に持ち込ませないようにして、少しでも力が緩んだと思ったら振り払ってください!」
『相手の力の加減なんて、ドール越しじゃ伝わってこないよ!』
「理屈じゃないんです、感じてください! 目の前のピンチにとらわれないで!」
私は古い映画の中にある台詞を思い出していた。実際に観たことはないのだけれど、その台詞だけは世話になった年上の先輩から幾度となく聞かされていた。台詞はさらに「もっと全体を見渡してみろ」という意味合いの言葉が続くのだが、それはトニーさんではなく私の役目だ。
常勝の余裕なのか、それとも指示に忠実にかろうじて身じろぎするニューオーダーの挙動のおかげか、クラブマンは組み合う体勢をまだ完全にはしていない。いやよく見れば、倒れるのを回避するとき地面についたニューオーダーの腕が邪魔になり、相手は攻めあぐねているようでもあった。もとから重量の半分くらいが腕部に集中したピーキーな造りになっているニューオーダーである。その極端に重い腕が地面に突き刺さって支柱の役割を果たし、思わぬ安定性が生み出されていたのだ。
耐えつづけてください──チャンスの時は必ずやってくるはずですから──
私は祈るように心の中で唱えた。
しかし、それは私のミスだった。
心で唱えるだけではいけなかったのだ。指示としてトニーさんに伝えるべきだったのだ。
インカム越しの息遣いが絶叫に変わったかと思うと、ニューオーダーは突如身じろぎするのをやめて、深く体を沈みこませた。そして私が「あっ」という声をあげるよりも早く、今度は腰をよじって地面に突き刺さっていた腕を引っこ抜いた。
攻めあぐねるクラブマンのようすが、トニーさんには弱者をいたぶって楽しんでいるように見えたのかもしれない。じわじわと追い込まれて行く恐怖に耐え切れず、ついにトニーさんはやみくもな反撃に出てしまった。
「ダメです、トニーさん!」
私の声は届いたはずだ。しかしニューオーダーの動きが止まることはない。
重い腕を遠心力で振りかざし、ふらつきながらムリヤリな殴打を相手に食らわせようとしていた。
その期を狙っていたのはクラブマンである。
組み付かれた状態での殴打など、人間の場合であっても効果的な攻撃にすることは難しい。ましてやドール、ましてや不慣れなパイロットでは、みずから体勢を不安定にして相手に有利を与えるだけのまったく無駄な行動となる。
クラブマンはニューオーダーの挙動を冷静にやり過ごし、上半身をうしろに退かせた。あえて相手の動きに逆らおうとはしないその動きに翻弄され、ニューオーダーの体勢はさらに崩された。
それはスモウ、またはジュードーの技のようだった。
遠心力に任せた攻撃を見事にいなされて、ニューオーダーの体は大きく回転し、背中から地面に叩きつけられる。
チャンピオンの妙技に、観客席から拍手と歓声がわき上がった。
応えるように頭上に両腕を突き立てるクラブマン。
あわれに地面に転がったニューオーダーは、それを見上げているしかない。
やがてバラバラだった拍手は一定のリズムを刻むようになり、チャンピオンにさらなるショーの展開を要求しはじめた。ボトミングの勝負が決するのは、どちらか一方が行動不能に陥ったときだ。つまり駆動系が完全に破壊された場合やパイロットがドールを放棄した場合などに試合は終わる。だが逆に言えば時間切れや判定勝ちもないので、続けようと思えば永久に続けることもできる。だからチャンピオンにはボトミングというショーを演出するエンターティナーとしての資質も要求された。相手が地面に横たわりもはや勝者が決まったこんなときでも、観客が求めるのであれば、チャンピオンは試合を継続せねばならないのである。
クラブマンが、突き立てた腕をニューオーダー目がけてゆっくりと振り下ろす。歓声が、そのハサミ状の手が機体を打ちつけるのに合わせてどよめいた。衝撃に揺れるニューオーダーの機体。しかしダメージは極めて軽微で、装甲を軽くヘコませた程度だ。
またクラブマンの手が振り上げられ、そして打ちつけられる。同じようにどよめく観客たち。まるで鍛冶屋の職人でも気取るかのように、クラブマンは単調な作業を繰り返した。攻撃としてはまったく意味をなさないものであるが、それが今日のチャンピオンの演出らしい。そんな単純な打撃こそが、ハシエンダの人々には受けがいいことを知っているのだ。
「トニーさん! 返事をしてください、トニーさん!」
呼びかけに、すぐに答えは返ってこなかった。横たわったニューオーダーは重い腕を投げ出し、クラブマンの打撃に身をさらすのみである。
「トニーさん!」
『──リン────』
しぼり出すような声が聞こえた。悔しさと恐怖がないまぜになった、弱々しい声だった。
『リン──すまない。君が整備してくれた機体を、上手く扱えなくて──』
「そんなことはいいんです! ケガはしていませんか? その状態で脱出するのは危険ですから、まずは降伏の意志を伝えて──」
『降伏? 私の負け、なのか──?』
「残念ですが、そう判断するしかありません──」
もちろんニューオーダーの機体性能を考えれば、立て直す方法はいくつかあっただろう。でも相手の攻撃に耐えられず、不用意な戦い方をした先ほどのトニーさんを冷静に分析すれば、これ以上の試合続行は不可能だという結論しか導き出すことしかできない。
『そうか。私の資質では、ここが限界か』
「いえ、今回は準備が足りませんでした。仕方がないんです、トニーさんのせいじゃありません」
『君がそんなあきらめたようなことを口にするなんて』
え? と、私はうつむきかけていた顔を上げた。クラブマンと打撃音と観客たちの声の合唱がうるさい中、トニーさんの声のトーンが急に変化したことに驚いたのだ。
『あきらめず懸命に生きろと言った君が──』
トニーさんは、地球で別れたままになっている家族をすぐに吹っ切ることはせず、まずは一生懸命生きることが大切なんじゃないかと言った、私の言葉のことを言っているのだ。
あの時あんな風に小生意気なことを言った私が、今ここでは「仕方ない」と説得しようとしている──それは確かに矛盾だ。
しかしトニーさんの声音にはそれを非難するようなニュアンスはなく、それどころか自己嫌悪するような苦渋の色が浮き出ているように感じられた。
『私のせいだな。まったく、いい大人が自分の娘はおろか同じくらいの子の望みにさえ応えてやれないなんて──』
トニーさんの言葉の最後のほうには、かすかに笑い声のようなものが混じっていた。
けれどそんな声もすぐに途絶えてしまう。
沈黙が続いた。
トニーさんはいま何を考えているのだろうと、私も思いをめぐらせた。
出会ったばかりの頃の印象からすれば、早々に降伏を認め逃げ出していてもおかしくはないトニーさんが、いまだそれをしない理由──
それは私の言葉のせいなのだろうか? それとも救ってあげることができなかったとわだかまりのある家族への贖罪を、ここで晴らそうとしているのだろうか?
トニーさんはいま、自分自身とも戦っているのかもしれない。
ボトミングでチャンピオンと対しながらもなお、地球を離れたあの日以来、ずっと弱さを抱えていた自分とも対していたのかもしれない。
私はじっと、インカム越しに耳を凝らした。
会場では、単純なショーアップに飽きてきた観客たちの歓声が、そろそろ怒号に変わりはじめていた。
『──そうだ、必殺技』
「え──?」
だしぬけに聞こえてきたのは、あまりにも意外な言葉だった。
『ニューオーダーには、まだ、必殺技がある』
「いやでもあれは──私のおふざけと言うか、有利に立ったときの演出として用意していたもので──」
トニーさんが言っているのは、ニューオーダーの整備の最終段階で私が追加した装備のことだ。ほんの思いつきのたわむれでしかないものなので、私は冗談めかしてそれを「必殺技です」とトニーさんに伝えていた。
『必殺技はこういうときにこそ使うものだろ、リン』
「あれは見た目の派手さだけを考えて用意したもので、攻撃の手段としては過度な期待はしないでくださいって言ったじゃないですか!」
『やってみる──!』
「トニーさん!」
観客たちの怒号を受けて、ついにクラブマンはとどめをさすべく攻撃方法を変えた。腕をただ叩きつけるのをやめて、今度はハサミ状になった手でニューオーダーの関節部分を切断しようと狙いを定めた。リズミカルなドラミングのようだった打撃から一転、片腕を水平に持ち上げたいわゆる正眼の構えで、クラブマンはピタリと静止した。
試合は、華やかなフィナーレを迎えようとしていた。
だがまさにその時、ムクリと上半身を持ち上げたのはニューオーダーである。重々しく片腕を振り上げ、最後のあがきとばかりに再びクラブマンに向けて殴打を試みる。
それに対してクラブマンは冷静さを崩すことなく素早く動き、構えた腕とは逆の腕でニューオーダーの攻撃をガードした。
だがその一撃はトニーさんのフェイントだった。
もう一方の腕が、間髪いれずクラブマンの頭部目がけて打ち出されていた。
フェイントに対応していたクラブマンは、一瞬の無防備をつかれる形となった。
『くらえ必殺の──』
コクピットで叫ぶトニーさんの声が聞こえた。私は思わずギョッとする。
必殺の? トニーさん、まさか私が追加装備のコードネームとして伝えたあの名前を叫ぶつもりじゃ────
『ロケットインパクトーーーーー!』
ニューオーダーの腕が、その先端の拳が、クラブマンの頭部に叩きつけられる。
同時に拳の中に詰め込まれていたロケット用の燃料が一気に燃焼、あたりはまばゆいばかりの光に包まれた。
私が用意した「必殺技」。
コードネーム、ロケットインパクト。
ドール相手にダメージなどほぼ期待できない見た目の派手さだけが取り得のかくし芸が、その思惑どおりに炸裂した瞬間だった。
「いやーまさか、あのパンチが勝利の鍵になるなんて思いもしませんでした」
「パンチ?」
「すみません間違えました。ロケットインパクト、です」
試合が終わった会場から行動不能となったクラブマンが運び出されていく。私とトニーさんは、誰もいなくなった客席からその光景を眺めていた。
苦しまぎれだった私たちの「必殺技」は、思わぬ逆転劇を生んだ。
チャンピオン・クラブマンのパイロットには、火をともなう爆発的な化学反応に対して何らかのトラウマを持っていたらしい。溶接工だった時代にケガをしたからだとか、幼い頃に見たパニック映画の影響だとか噂はたくさんあったけれど、それらすべての真偽のほどは明らかではない。中には花火大会の日に憧れの人からひどい振られかたをしたというものまであった。なんにせよ、トラウマと言ってもそれほどシビアなものではないらしいので、「必殺技」によって生まれたチャンピオンの“隙”はほんの一瞬のことだっただろう。
しかしあの時トニーさんはヘンなスイッチが入った状態で、暴走したテンションのままに次々と攻撃を繰り出し、幸運にもそれらはことごとくヒットして、ついには相手を行動不能に追いやったのだ。まさにラッキーが積み重なった結果なので、この勝利はチャンスを活かしたと言うよりも、チャンスの方が転がり込んできてくれたという感じだろうか。
「でもまぁ、勝ちは勝ちだ!」
一時は声を震わせていた人が、いまは得意顔で胸を張っている。私は思わず吹き出すようにして笑った。
「開き直りましたね、トニーさん」
「ああ、開き直った。リンが言ったように自棄を全部吐き出してしまったようだよ、気持ちが軽いんだ」
言葉通りにトニーさんの声は軽やかだった。私はトニーさんの横顔を見つめ続ける。
「それに、必死になって生きることのやり方もわかったような気がする。リン、君のおかげだ」
「私はお肉のためにやっただけですよ」
今度はトニーさんが吹き出して、笑顔をこちらに向けた。全然似ていないのに、ふいに私はお父さんのことを思い出した。
「これからどうするんです? チャンピオン」
「目立ちすぎちゃったからね。借金取りもまたやってくるだろうし、しばらくはボトミングで賞金稼ぎかな。あ、そのためには新しいセコンドを探さないと」
私を見るトニーさんの目が、かすかに曇った。そんな表情を見せる気持ちと同じようなものが私の中にもあったけれど、表情には出さず、私は一番の明るい声で返す。
「そうですよ! 私はもう、基地に帰っちゃうんですからね!」
「うん──」
微妙な沈黙が私たちの間に流れた。
いちばん苦手な気まずい空気が降りてくる。
私はその場から立ち去るべく、ゆっくりと歩き出した。トニーさんに顔を向けたままのうしろ歩きだ。
「じゃあ──お元気で」
「リンも。──そうそう、フィッシャーマンズアレイの肉屋のジャンさん。もう一度捜しておくよ」
「お願いします」
私は手を振り、トニーさんに背を向けた。
進む先には、パイプが入り乱れて地下迷宮のようになったハシエンダの風景がある。
しかしいつの間にかそれにも慣れた私は、迷うこともなく、もといた場所へと帰って行けるのだ。
ハシエンダから戻ったその日。
基地で行われたお肉パーティは大盛況のままに終了した。
フェイクマツサカは滅多に味わえる食材ではないし、ボトミングの優勝賞品として用意されていたのは莫大な量であったので、最終的な参加者はかなりの人数に達した。
思う存分料理を振る舞うことができた私には、いま、充実感しかない。
ハシエンダでお肉を受け取るとき、話のタネにと見学させてもらった食肉合成工場で飼育されていた大量の昆虫のことは、この際黙っていよう。
次の日から、私は通常の任務へと戻った。
油くさい整備ドックで、軍用ドールと格闘する日々がまたはじまったのだ。
やはりこちらの方がしっくりくるなぁと実感しつつも、ロケットインパクトみたいなものを組み込めないことは少し残念かも、と私は思ったりする。
「リン」
よじ登っていたドールの足元から声がした。
見下ろすと、そんなに長く会わなかったわけではないのに、ひどく懐かしく感じるエルマさんの姿がそこにあった。
「エルマさん! すみません、ずっと留守にしちゃって」
「そうね。仕事がかなりたまってるから、しばらくは時間外での作業も頼むことになるわ」
「了解です! ──あ、そうそうエルマさん」
「なに?」
「人は生きるために食べるのか、食べるために生きるのか。答えがわかったような気がするんですよ、私」
「へぇ、聞かせてもらいたいわね」
見上げてくるエルマさんの目を見つめ、私は得意満面に答える。
「一生懸命やったあとのご飯は美味しい。人は、それだけで充分です!」
![]()